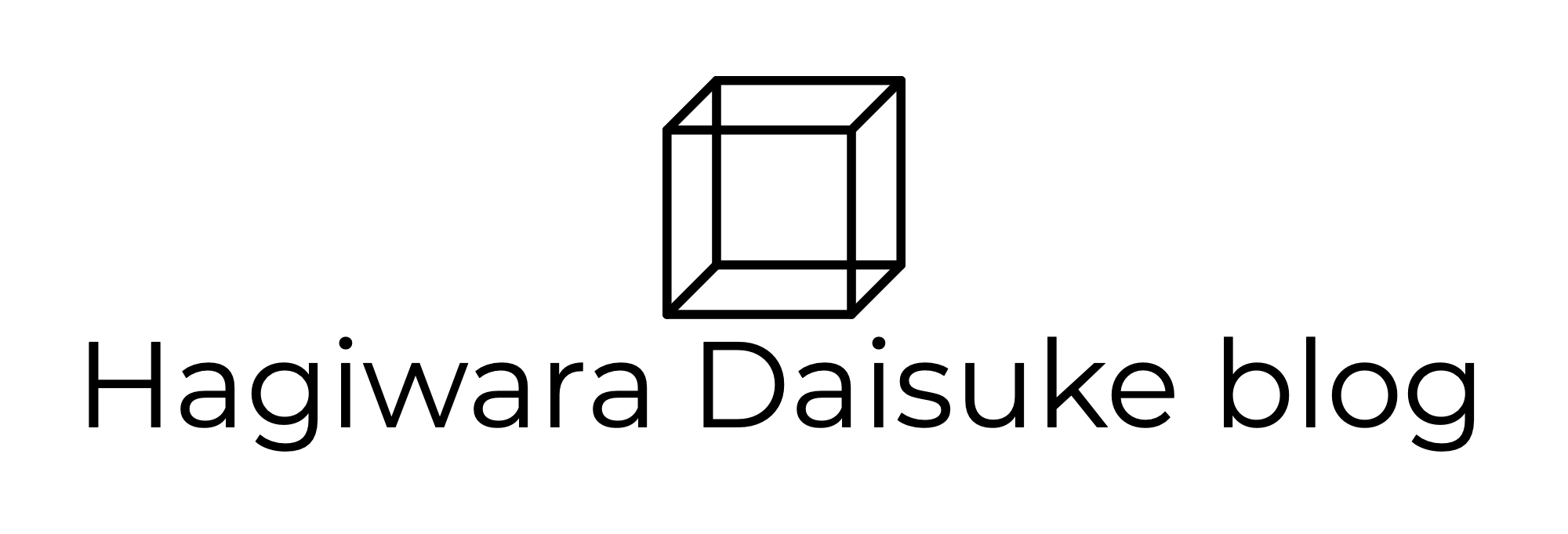僕は一人家路を急いでいた。
気温は大分上がってきたがまだ肌寒い日が続いている。
駅から約10分の道のり、安アパートの2階が僕の家だ。
やたらと足音が響く鉄製の階段を上がる。
廊下を見ると家の前で座り込んでいる子供達。
手には携帯ゲーム機を持っている。いつものことだ。
僕は溜息をつきながら、子供達の前へ行き一言。
「あのなぁ…いつも言ってるけど、人の家の前で遊ぶなよ。」
子供達は目も合わさずに言った。
「は~い。」
「行こうぜ。」
やり場のない感情を抑えながら、鍵を開ける。
電気も付けずベッドに寝転んだ。
今日の面接を思い出して、さらに溜息が出る。
今日もダメそうだな…
僕はどちらかと言うと、ツイてない人間だと思う。
大学を卒業し新卒で入社した会社はあえなく倒産。
そのあと転職するも、ロクな会社と出会えずに仕事先を転々とする日々。
就職の道は厳しく、派遣社員として様々な会社で綱渡りのような生活を続け、
気付けば27歳になっていた。
結婚はしていない。
こんな生活ではできるはずもないし、彼女と呼べる人もいない。
社会から迫害されているような気さえしていた。
ふて寝しようとしていたら、ふいに携帯電話が鳴る。
鞄の中をあさり、携帯電話の表示を見た。
加藤博樹
大学時代の友達だ。
「もしもし。」
「久しぶり、今大丈夫か?」
「大丈夫だよ。」
「原田、今就活してるって話聞いて電話したんだが、どんな感じ?」
「あぁ就活してるよ。」
「そっか、紹介したい仕事があるんだが近々会わないか?。」
「いいよ。じゃ明日は?」
「悪いな。俺は忙しいんだ。今度の火曜日でいいか?」
「了解。じゃそういうことで、場所は?」
「原田の家に行くよ。じゃあな。」
大して何も考えずに電話を終え、携帯電話を鞄に放り投げ僕は眠った。
加藤と約束した火曜日、インターホンが鳴る。
僕がドアを開けるとスーツ姿の加藤が笑顔で言った。
「お疲れ様さん。」
「おう、いらっしゃい。」
加藤とは同い歳で、大学の時何かと会うことが多く仲良くなっていった。
彼はもう結婚し家庭を持っている身だ。
会うのは相当久しぶりだった。
「ビールでいい?」
冷蔵庫を開けながら聞くと加藤は座りながら言葉を返した。
「いや酒はいいわ。コーヒーとかある?」
「インスタントならあるよ。」
「それでいい。」
インスタントコーヒーをポットのお湯で用意し、加藤に出しながら話した。
「結婚して何年だっけ?」
「5年だよ。」
「どうよ、結婚生活は?」
「そうだな…。まぁ可もなく不可もなくってとこかね。何とか上手くやってるよ。」
「そっか。」
「原田はどう?」
「全然ダメだね。仕事が決まらなくて。まだ失業保険で何とかなってるけど。」
「なるほどな。今はなかなか厳しいからな。」
何となく雰囲気の怪しい加藤に僕は言った。
「あ、言っとくけど宗教には興味ないから。」
「違う違う。安心してくれ、仕事の話だよ。」
「ならいいんだけど。」
「原田、免許持ってたよな?」
「一応持ってるよ。」
「よし。仕事ってのは簡単に言うと車の運転だ。」
「いや、無理だって。5年以上ブランクあんだぞ。」
「大丈夫、心配ない。詳しくは担当者から話をさせるよ。明日暇か?」
「残念ながら暇だ。」
「じゃ13時に迎えに来るわ。一応これに目を通しておいてくれ。」
加藤は僕に一冊のパンフレットを差し出した。
僕はパンフレットを受け取り、開いた瞬間
加藤の携帯電話が鳴った。
携帯電話を持って慌てるように外へ出る。
数分後、無表情で戻ってくると鞄を持って僕に言った。
「悪い。会社に行かなきゃならんのでまたな。」
「え?もう行くの?」
「詳しくは明日話すよ。コーヒーありがとう。」
加藤はまるで何かに追われるように玄関を出て行った。
僕は、加藤が結局口をつけなかったインスタントコーヒーを手に取り、
電子レンジに入れ少し温めた。
コーヒーを飲みながら、テーブルの上にあるパンフレットを開く。
大手の自動車メーカーのパンフレットで、
内容を詳しく見ても特に変わったところはない。
当然、僕が明日任されるであろう仕事内容についても一切説明書きのようなものはなかった。
そのままパンフレットはテーブルに置いて、
僕は一人の時間を音楽を聴いて過ごした。
翌日、インターホンが鳴り目が覚める。
寝ぼけながらドアを開けると加藤が立っていた。
「おはよう。迎えに来たぞ。」
時計を見ると朝8時だ。
「…こんなに早く迎えに来るとは聞いてないぞ。」
「悪いな。待ってるから準備してくれ。」
「分かったよ。じゃ15分待って。」
急いで準備をし、僕は加藤の車に乗った。
走り始めた車の中で加藤は言う。
「コーヒー買っといたから飲んでくれ。」
見ると助手席のドリンクホルダーに缶コーヒーが入っていた。
「ありがとう。」
僕は手に取りコーヒーを飲む。
元通りフタをし、ドリンクホルダーに戻した。
僕がコーヒーを飲むのを待って原田は話しかける。
「なぁ原田。」
「ん?」
「お前本当に良いヤツだな。」
「なんだよ、急に。」
「いや、何でもない。」
加藤はそう言った後、何も言わすハンドルを握っていた。
何だか加藤はいつもの表情と違って見えた。
僕と一緒とはいえ、会社に行くわけだし仕事モードなんだろう
そう考えていたら急に眠気がやってきた。
それも今まで感じたこともない強烈な眠気だ。
朦朧とする意識の中加藤を見る。
加藤は悲しそうな目で僕を見て言った。
「すまん…」
目が覚めると僕は一面真っ白な部屋にいた。
動こうとするが、身動きができない。
僕は手足を縛られていた。辺りを見渡すが誰もいないようだ。
頭に何かヘルメットのような物を被らされているらしい。
頭がやけに痛んだ。訳が分からなかったが、これが加藤の言う仕事だろうか。
何にしても加藤にハメられたことは間違いないだろう。
僕は何よりそれがショックだったし、どうしようもない程悲しかった。
少しすると、ドアが開き白衣を着た男が入ってくる。
加藤ではなかった。
白衣の男はまるでテーブルの上の文房具を見るような目で僕を見ていた。
やがて近づきながら話しかける。
「はじめまして、原田真さん。お目覚めのようですね。
私はこの研究所を管理している坂崎と申します。」
坂崎と名乗る男は、神経質そうなインテリな男だった。
「原田さんには、ちょっとお仕事をして頂きます。ご心配は無用です。
ちょっとした旅行だと思って頂ければ結構ですよ。」
そう話した後、目つきを変えて付け加える。
「…ただし、注意点が二つあります。一つはこちらの指示に必ず従って頂くということ。
もう一つは…」
坂崎は改めて僕の目を見て言った。
「死なないことです。」
僕は何か言い返そうとしたが、
声が出なかった。
必死に声を出そうとしている僕に坂崎は言った。
「あ、そうそう。今原田さんは話せませんよ。
我々がコントロールしていますので。」
???
「さぁそれでは行きますか?大丈夫ですよ。
ミッションはきちんとプログラムされます。では、お気をつけて。」
坂崎の声の残響とともに僕はまた意識を失った。
目覚めると僕は車の中にいた。
見慣れない車の運転席に座っている。
「原田様、お目覚めですね。」
車のスピーカーから男の声がする。声の感じからして坂崎の声だ。
「あ、あ。」
さっき声が出なかったので試しに声を出してみる。声は出た。
そんな僕を無視して坂崎は感情のない声で続けた。
「この世界は、いわばパラレルワールドです。
原田様の肉体は現実の世界にありますが
今原田様がいらっしゃる世界と感覚は全く変わりません。」
僕は体をつねってみた。確かに坂崎の言う通り、普通に痛みは感じる。
「さて、原田様にお願いしたいのは簡単なお仕事です。
カーナビゲーションシステムを見て頂けますか?」
中からだと車種が分からないが、カーナビは普通に取り付けられている。
「このカーナビゲーションシステムは、テスト用の物です。
目的地を示しますので、その場所に行って下さい。
基本的にはそれだけです。また連絡します。では。」
通信が途絶えた。
僕は全く状況が飲み込めないまま、カーナビを見た。
確かに目的地が設定されているようだ。
溜息をつき、車を走らせる。
走り始めてから気付いたが、このカーナビは音声が出ないらしい。
自分の場所と目的地までのルートだけを示した、とてもシンプルな物だ。
周りの景色を見ながら走る。
ある程度走り続けた後、自分が感じている違和感が徐々に明確になってきた。
対向車はもちろん、前後にも全く車は走っていない。
疑問に思いながらも走り続ける。
スタート地点は、高速道路だったがカーナビに従い一般道へ。
建物や広告、看板等はかなり正確に作られている。
正確に作られていれば作られているほど、何だか妙に不気味だった。
パッと見、僕が生きている世界と変わりないが人の気配が全くないのだ。
内心不安を感じながら、カーナビの示す目的地に到着した。
これで現実に戻れる。
車を停めた後、スピーカーから坂崎の声が聞こえる。
「ご苦労様でした。では次の目的地です。」
「え?終わりじゃないんですか?」
戸惑いながら聞いた僕に坂崎は答える。
「誰が終わりと言いましたか?説明が遅くなりましたが、
このミッションは人間の限界をテストするためのものです。
まだまだ走って頂きます。システムをご覧下さい。次の目的地が表示されているはずです。」
「…ということは、倒れるまで走り続けるのか?」
「まあ、そういうことになるかもしれませんね。しかしご心配はいりませんよ。
この車のガソリンは無限です。そして、もうお気付きでしょうがその世界に生命体は存在しません。
現実世界をコピーした空間です。ではご検討をお祈りしております。」
「おい、ちょっと待ってくれ。
何も聞いてないし、こんなの無茶苦茶だ。おい!」
そのままノイズとともに、坂崎との連絡は途絶えた。僕はひたすら走り続けた。
目的地にたどり着くとすぐ次の目的地を示す、悪魔のようなカーナビと一緒に。
326回目のルートで高速道路を走っている時、
流石に限界を感じサービスエリアに寄る。
不安だったが、人がいないだけで通常の世界と同じように機能していた。
ポケットに手を突っ込むと小銭がいくらか入っていることに気付く。
そういえば、何も飲み食いをしていない。
食料品の自動販売機もあったが、
食欲は全くなかったので僕はとりあえず自動販売機でコーヒーを買った。
一口飲み、そのままテーブルにもたれて少し目を閉じてみる。
僕はただ現実世界に帰りたかった。
あの面倒臭い現実世界が今は何よりも恋しい。
でも
今まで感じてきた感情は乾いてしまっているように思った。
”もうどうでもいいや”
そんなことを思いながらコーヒーを飲む。
気が付くと僕は泣いていた。
たった一人で僕は泣いていた。
今まで悩んでいたことが、どれだけつまらないことだったのかが身に染みる。
僕は涙を流したまま…
気を失った…
目を覚ますと、真っ白な部屋に僕は横たわっていた。
周りを見渡していると加藤が声をかける。
「原田!大丈夫か…?」
「…よく分からないけど、どうやら生きてるみたいだな。」
「もちろんだ。ここは現実の世界だよ。坂崎が勝手に作成したプログラムは全部俺が解除したよ。」
「解除…そうか夢じゃなかったんだな。」
「こんなはずじゃなかった。本当にごめん…」
加藤は心から謝る雰囲気で頭を下げる。
「原田が体験した世界は、
坂崎が作ったイメージの世界で脳に信号を送ることで成立させていたんだ。」
「坂崎は?」
「違法行為を繰り返してたことがバレて警察に捕まったよ。本当、原田に何て謝ったらいいか…」
「やめてくれ、全部許すからもう一度やり直そう。僕は大事な友達を失いたくない。」
僕が肩を叩いて言うと加藤は泣きながら何度も頷いた。
翌週、
銀行口座を確認すると、500万が振り込まれている。
こんなあぶく銭はいらない
そう思った僕は全額を震災の義援金として窓口に寄附をした。
今まで生活が厳しすぎて義援金を送ることができなかったので少し気持ちが楽になった。
”仕事なんてまた一から探せばいい”
そんな風に考えていた。
現実に帰れた日、僕は土のように眠りにつく。
翌日、目覚めて感じた
ささやかな、愛おしいありふれた日常。
窓から外を見ると陽だまりの中で子供達が遊んでいる。
相変わらず迷惑だったが、僕は彼らを見て思わず笑ってしまった。
身の回りの風景がどうしようもなく暖かく感じる。
この光のカケラをいつまでも忘れずにいよう
僕は心から思った。
陽だまりの中で。

萩原大介(ハギワラダイスケ )切ないメロディーで心の音を鳴らす孤高の唄い人。 「風景の唄」「希望の唄」「夕凪の唄」アルバム3枚全国リリース。 FMaiai毎週金曜日12時〜番組パーソナリティ。 歌を歌いながら文章を書いています。 blog毎日更新。 短編小説は不定期に新作をアップ。