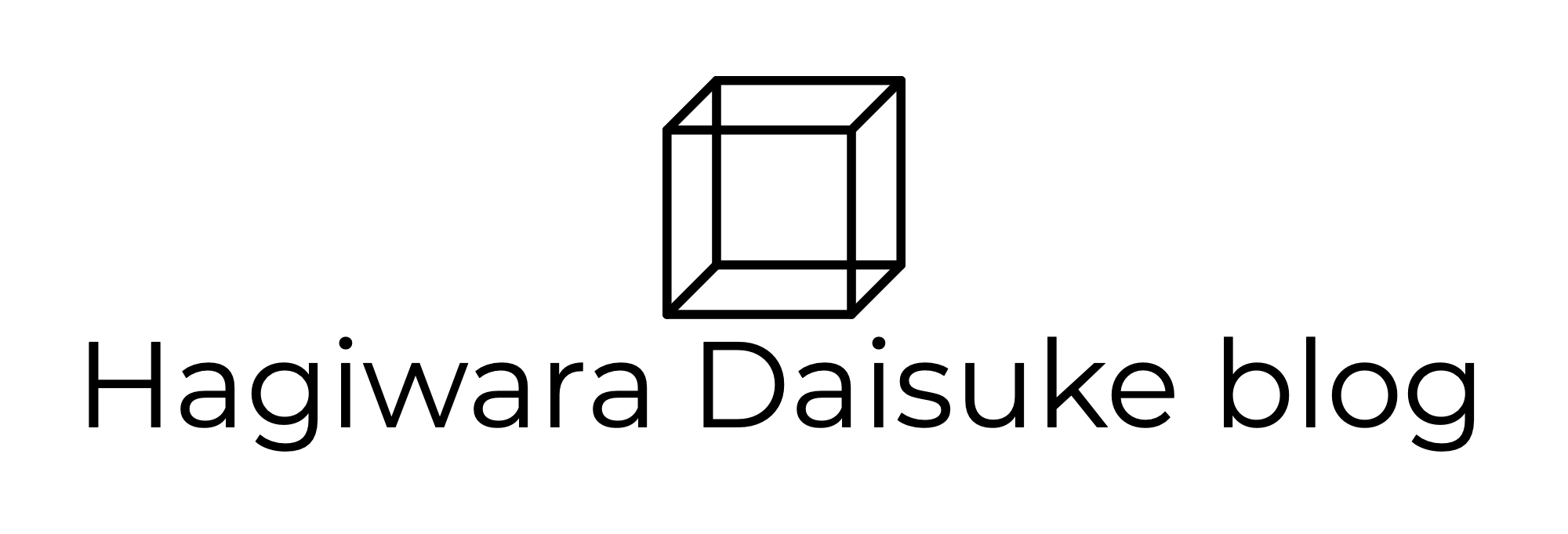僕は旅をすることが好きだった。
全国を歩きまわり、様々な人達や文化に触れ合う。
出来ることならそんな仕事につきたかった。
しかし理想と現実には途方に暮れるほどの距離があった。
僕は会社勤めの身でろくに有給休暇もとれず、ひたすら働いていた。
その中で自分がどんどん擦り減っているのを感じたのは随分と後の話だ。
自分の心の中は今にも破裂しそうだった。
でも僕は働き続け、気が付けば今まで感じていた希望や夢を完全に諦めるようになっていった。
ある日、懐かしい友達の遠野から携帯に着信があった。
「はい。もしもし。」
「圭吾久しぶり!」
「本当久しぶりだな~。どうしたの?」
「いやいや、元気かなと思って。」
「何だそりゃ、ただひたすら働いてるよ。」
「そっか…よかったら近いうち会わないか?」
「構わないよ。明日はどう?」
「了解。じゃ明日の夜会おう。また連絡する。」
そう言った途端、電話は切れた。
翌日、カフェで遠野と話す。
一通り他愛もない会話を交わした後で遠野は切り出した。
「実はお前にプレゼントしたいものがあるんだ。」
「ん?何?」
「これなんだけど」
遠野が鞄から取り出したのは一枚の封筒。
中を見てみると電車の乗車券らしき物と簡単な説明書きが入っていた。
「ん?何これ?電車の切符みたいだけど行き先も期限も書いてないぞ。」
「そのチケットは、どこへでも行けるチケットだ。」
「…どの駅でも降りることができるってこと?」
「そうだ。まぁ駅という訳でもないが、詳しくは同封してある説明書きを読んでくれ。」
「何だか胡散臭いな。こんなチケット見たことないし、会社名すら入ってないじゃんか。」
「会社名は説明書きに書いてあるよ。ちゃんとした旅行会社だ。
気晴らしにどっか出掛けてこいよ。お前酷い顔してるぞ。」
「う~ん、それもそうだな。じゃありがたく。」
早速説明書きを読もうとしたら、遠野は後でゆっくり読むように言ってきたので黙って従う。
その後少し話して僕らは別れた。
家に帰り、封筒を改めて開けてみる。中の説明書きはこうだ。
このチケットはあなたの行きたい場所へ行けるチケットです。
以下の説明に従って会員登録を済ませて下さい。
こちらから追って集合場所、日時をお知らせ致します。
尚、お客様自身で場所を選ぶことはできません。何卒ご了承下さい。
お客様が今一番行きたいと思っている場所へお連れ致します。
お客様にとって心休まる素敵な旅となることでしょう。
株式会社ミライトラベル
株式会社ミライトラベル…こんな胡散臭い会社名聞いたこともない。
遠野に騙されたか?大体自分で行き先を決められない旅って何だろう?
怪しい説明書きではあったが、妙に気になる何かを感じていた。
このチケットについて調べてみたが結局何も情報を得ることはできなかった。
でも僕は興味本位でこのチケットを使い旅をすることに決めた。
よく分からないが行くべきだと感じたからだ。
翌日会社へ連絡し、しばらくの間休みをもらうよう伝える。
会社側は嫌がったが
今まで一切勝手も言わず会社に従っていたことで何とか希望を通すことができた。
旅の申し込みの為、説明書きにある通りに会員登録を済ませる。
指定されたメールアドレスに氏名と生年月日を送るだけの簡単なものだった。
しばらく待つが反応はない。
返信を待つ間
冷蔵庫からビールを取り出し、簡単な夕食をとる。
気になったのでインターネットでミライトラベルのことを調べてみると、
確かに存在している会社だった。
だが、妙なことに事業展開について明確な記載は一切なく
「ただ存在している会社である」
という情報しか得ることができなかった。
これ以上調べるのを諦め、本を読んでいると携帯にメールが届く。
さっきの登録完了に対するメールだ。
ムラセ ケイゴ様
株式会社ミライトラベルでございます。
この度は弊社のプランにご登録頂き、誠にありがとうございます。
11月23日19時
株式会社ミライトラベル本社1階のロビーまでお越し下さい。
メールは短い文面で終わっていた。
これじゃ旅の期間も何も分からない。
今日は11月12日
まだ期間があるからまた考えることにして僕は眠った。
それから時は過ぎたが、出発前日になってもミライトラベルからは何も連絡は来なかった。
それはつまり、もうこれ以上連絡する必要がない
ということを意味するのだろう…まぁいい。どうせこっちには時間があるのだ。
旅行会社に任せよう。
半ばヤケになってるところもあったが心のどこかで何かに期待している自分がいた。
11月23日
西新宿にある株式会社ミライトラベル本社へ向かう。
荷物は迷った挙げ句、リュック一つに最小限の物を詰め込んだ。
指定されていた本社のエントランスに着くと、
しばらくしてスーツ姿の男がこちらに向かって歩いてくる。
「ムラセ ケイゴ様ですね?」
「あ、はい。」
「お待ちしておりました。ご案内致します。どうぞこちらへ。」
丁寧な対応だが目を離すと忘れてしまうような不思議な雰囲気を持った男だ。
ところで…なぜ僕が村瀬だと分かったんだろうか?
不思議に思ったが、気にしないことにした。
…どうせこれから不思議なことばかりが起きるんだろう…
そう考えるようにし、僕は驚かないよう身構えていた。
そして
その予想は…見事なまでに当たっていた。
男の後をついていきエレベーターに乗る。
地下三階でエレベーターは止まった。
「どうぞ。」
僕は黙って頷き、エレベーターを降りた。
…思わず言葉を失った。
会社の地下のはずなのにエレベーターを降りた所から駅になっており、列車が止まっている。
「これに乗るんですか?」
僕は男に尋ねる。
「左様でございます。トオノ様のご予約されたプランはこの列車に乗って向かって頂きます。」
男は笑顔を浮かべながらもどこか機械的に答える。
僕はずっと引っかかっていたことがあり尋ねた。
「あの一つ質問いいですか?」
男は笑顔を崩さず答える。
「どうぞ。」
「あの、このチケット1枚で往復できるんでしょうか?」
「当プランに関しまして、帰りのチケットは必要ございません。」
「どういうことです?」
「旅に出られたら、お客様ですぐご理解頂けるかと思われます。どうかご安心を。」
男の笑顔が気味悪かったが、これ以上確認するのも面倒だったので僕は黙って頷いた。
だがその他に気味悪いことがあった。
その駅には、僕とその男以外は誰もいなかったのだ。
胡散臭いことには間違いないが、
なぜか引き返す気にはならなかったのでそのまま男の案内に従って列車に乗り込む。
列車の中はかなりレトロな雰囲気だ。
乗り込んだ後、不思議と不安はなかった。
しばらくして列車は動き始める。
僕は肘をついて窓の外を見た。
いつの間にか地上に出ていたらしく夜の景色が見えた。
美しい夜の光は僕を包んでいく。
家々の夜景が窓いっぱいに広がり、
安堵感と不安と暖かさ、それと同時に物悲しさを感じていた。
少し疲れを感じ始め、シートにもたれ目を閉じていた。
そうだ、今旅をしてるんだ。
そんなことを考えながら、色んなことを思い出していた。
今まで傷つけてしまった人達のことを。
「…様」
「ムラセ様」
誰かが僕の肩を叩いている。
ふと目を覚ますと、さっきのスーツの男だ。
どうやら、僕は眠ってしまっていたらしい。
「あ、すみません。チケットの確認ですか?」
「いえ、違います。間もなく目的地へ到着します。」
「どこに?」
「それはムラセ様ご自身でご確認下さい。」
それだけ言い残すと、スーツの男は行ってしまった。
相変わらず不思議な男だ。
声に感情が全く感じられない。
まだ寝ぼけてぼーっとした頭でいたが、窓の外を見て一気に目が覚めた。
夜が…明けている?
列車に乗り込んだのは19時半くらいだ。
そんなに寝た気はしないのだが、時計を見ると列車に乗った19時半で止まっている。
おかしいな…電池換えたばかりなのに…壊れたかな?
やがて列車は駅に着いた。
列車を降りると、懐かしい風景に包まれる。
ホームの看板を探すがどこにも見当たらなかった。
駅の改札を出ると誰かが手を振っているのが見えた。
僕は小学生の頃に父親を亡くし、母親に育てられた。
信じられないことに、
そこで手を振っているのは…
死んだはずの僕の父親だった。
改札には僕しかいなかったから、こちらに向かって手を振っているのは間違いない。
そのまま近づく。
父親は笑顔で話しかけてきた。
「圭吾。大きくなったな!俺が誰だか分かるか?」
「父さん?」
僕が唖然としながら言うと父親は豪快に笑った。
「何でここに?」
「何でって、圭吾が会いたいと思ってくれたから俺はここにいるんだよ。」
「どういうこと?」
「まぁ細かい話は抜きにしよう。そこに座れよ。」
父親は駅のすぐ裏にある公園のベンチを指差した。
「…あれ、あの公園どっかで見た気が。」
「ここでよく遊んだろ?覚えてないか?」
そうだった。
僕はこの公園で父親とよくキャッチボールをしたのだ。
「懐かしいね。」
「お!思い出したか!圭吾はやればやるほど上手くなってったからな。
どうだ?母さんは元気か?」
「元気にしてるよ。最近あんま連絡してないけど。」
「何だ、一人暮らしか?頼むぞ、母さん頼れるのは圭吾しかいないんだからな。腹は減ってるか?」
「あ、そういえば今日何も食べてないな。」
「よしじゃ帰るぞ。」
「帰るってどこに?」
「帰るのは家に決まってるだろ?」
そのまま、父親が運転する軽トラックに乗せられ家へ向かう。
しばらくすると実家が見えてきた。
しかし…本当は”前の実家”だ。
父親が亡くなった後しばらくして、この家は区画整理で取り壊されたはず…なのに。
目の前には確かに当時のままの家がそのまま建っていた。
車を止めて家に入ろうとする父親が声をかける。
「どうした?入らんのか?」
「あ、入るよ。ごめん。」
家に入ると、当時のままの玄関、家具、匂いに一気に包まれる。
僕はいつの間にか涙を流していた。
「どうした?家に帰ってきた途端泣く奴があるか。」
父親は背中をさすりながら笑った。
「まぁ、圭吾にとっては懐かしいだろうからなぁ。」
「え?」
「何でもない。さぁ今日はお前のために腕を振るったぞ。」
居間に入ると、懐かしい父親の料理が並んでいる。
僕は父の料理が大好きで、それを言うとよく母親が拗ねたものだ。
「美味そう!じゃいただきます!」
「おう、しっかり食え。」
懐かしい父親の料理。
美味かった。
美味くて涙が出た。
父親は満足そうに僕の顔を見ている。
「父さんは食べないの?」
「あぁ、俺は大丈夫。」
食事を済ませ、洗い物を片付け二人で他愛のない話をした。
…ここはどこなんだ?…
笑い合い話しながら当然のように起こる疑問を掻き消す。
しばらくすると、父親は立ち上がり言った。
「どうだ?久しぶりにキャッチボールでもするか?」
「行こう!食べ過ぎたし、消化しないと。」
「ははは。そうだな。」
父親の笑顔を見ながら思い出していた。
そうだ、父さんはよく笑う人だった。
父さんが笑うと家の中全部が明るくなった気がしてたっけ。
2人で駅近くの公園に行き、キャッチボールをする。
陽は傾いて夕暮れ時だった。
父親の投げるボールをしっかり受け止め、僕の投げるボールを父さんはしっかり受け止めてくれた。
その後父親は唐突に話し始めた。
「圭吾…すまん。そろそろ行かないと。お前はもう大丈夫だ。強く生きろよ。
俺はお前という息子を持てて本当に幸せだったよ。」
「父さん、いきなり何言ってんの?一緒に家帰ろうよ。明日には母さんも帰ってくるだろうし。」
父親は少し悲しそうな笑顔で言う。
「圭吾、お前には戻らなきゃならん場所がある。
そして、これから行かなきゃならん場所がたくさんあるんだ。」
話しながら父親は僕に何かを手渡した。
手のひらを開くと、父親がいつも身につけていたネックレスだ。
「圭吾、自分をしっかり持ってな。お前はどこへでも行ける。俺はいつも見てるから。」
夕日が父親の姿と重なってよく見えない。
「父さんちょっと待って!行かないでくれ!
まだ話したいことが、一緒にやりたいことがたくさんあるんだ。」
父親は笑顔で手を振ったまま、消えてしまった。
そしてその瞬間…
目が覚めた。
僕は…電車に揺られていた。
気付かないうちに泣いてしまっていたようだ。
目が熱く湿っている。
乗り慣れた電車の中。
人もたくさん乗っている見慣れた景色だ。
全部夢だったのか…
ぼやける意識の中、手のひらを見るとネックレスを握っていた。
…夢じゃなかった…
そうだ僕はどこへでも行ける。
少しだけでいい、前に進もう。
父親からもらった首飾りを握りしめて強く思った。
少しだけ前に進もう
僕は心からそう誓い、一人きりで思い切り泣いた。

萩原大介(ハギワラダイスケ )切ないメロディーで心の音を鳴らす孤高の唄い人。 「風景の唄」「希望の唄」「夕凪の唄」アルバム3枚全国リリース。 FMaiai毎週金曜日12時〜番組パーソナリティ。 歌を歌いながら文章を書いています。 blog毎日更新。 短編小説は不定期に新作をアップ。