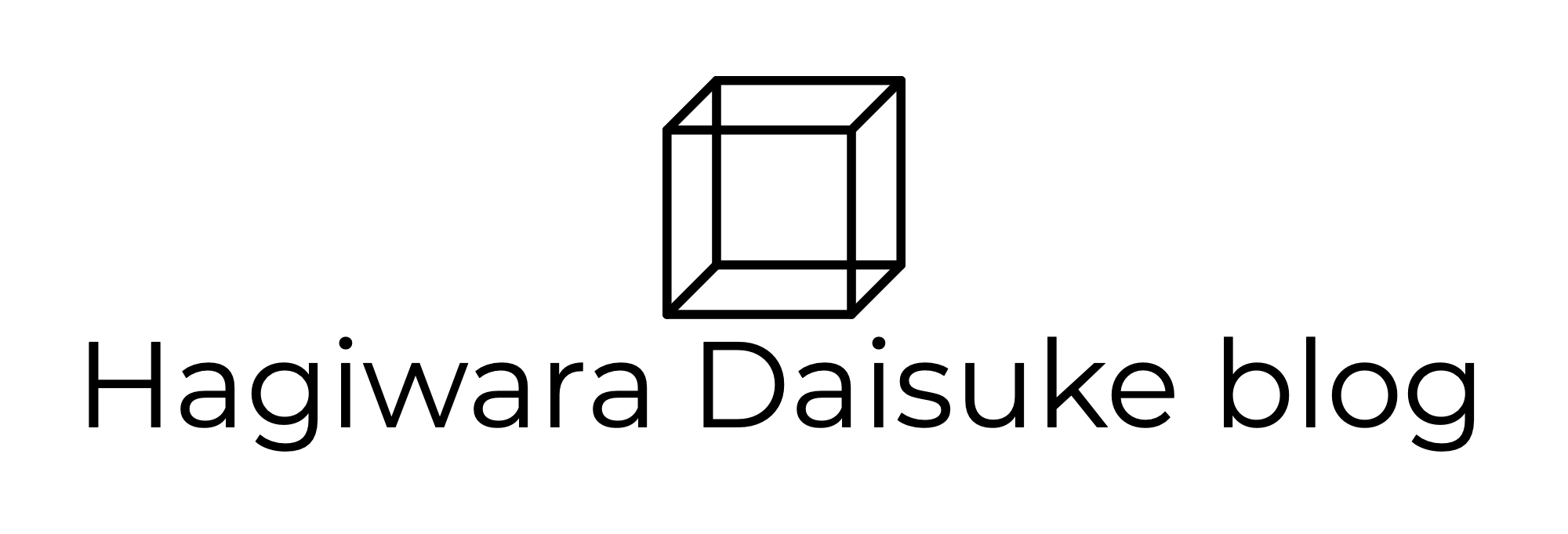冬の朝、僕はいつもの道を歩いている。駅へ向かう人波はとても速足だ。
そんなに急いで一体どこに向かうんだろう。
あの頃の僕はまだ19歳で
ただ漠然としたイメージだけを両手に抱え、東京にやってきた。
特に何がしたいわけでもなかった。
後になって気付いたことだけれど
あの頃の自分には人の痛みなんてまるで分らなかった。
1997年 春
“とりあえず大学へ行って先のことを考える”
という気にはなれなかったから、
“とりあえず働いてみる”ことにした。
片っ端から求人誌に目を通し、いくつかの会社にエントリーする。
高卒であることは思ったより不利にならなかったらしく、
就職活動を始めてすぐに
とある小さな広告代理店から内定をもらうことができた。
給料は安かったが、経験もなく高卒である僕を受け入れてくれることだけで十分満足していた。
仕事は淡々とこなした。
会社の仲間は、当時10代だった僕に優しくしてくれたし特に不満もなかった。
ただ人付き合いは面倒で、基本的に一人で過ごすようになり
そのせいで誰もが僕と距離を置いて接するようになっていった。
気が付けば、ただ何となく時間を過ごし毎日家と会社の往復のみ。
それが僕の人生だった。
ある日、仕事からの帰りポストを開けると珍しく母親から手紙が来ている。
「元気にやってますか?手紙が来てたのでそっちに送ります。」
と書いてあった。
中には、聞いたことのない名前の女性からの手紙が同封されている。
僕が通っていた学校は男子校だったので、心当たりなんてまるでない。
手紙にはこう書いてあった。
「突然のお便り失礼致します。あなたの歌を聴かせて頂きました。
今私が任されているライブイベントがありまして、是非お誘いしたいのです。
よろしければ一度お会いできませんか?」
最初、意味が分からなかったが僕は高校生の頃に歌を作っていて
当時いくつかのレコード会社や事務所に応募していたことを思い出した。
もちろん返事なんて全くなかった。
早々と諦めてしまったので、もう随分歌は歌っていない。
今さらとは思ったが、手紙は東京から来ていたし仕事以外は何も用がなかったので
“まぁ話だけ聞いてみるか”
と手紙に書いてあった事務所に電話をかけてみた。
感じ良く対応してくれた男性は手紙をくれた女性に取り次いでくれた。
「お待たせ致しました。ご連絡ありがとうございます。
是非お会いして打ち合わせをさせて下さい。
プロフィール用の写真があるので、当日はこちらからお声かけ致します。」
彼女は良く通る声で話した。念のため、僕の携帯電話の番号も教えておき
新宿にあるホテルのラウンジで待ち合わせることになった。
待ち合わせ当日、約束のホテルへ向かう。
ラウンジは平日だっせいか空いていた。
電話の女性らしき人物は見当たらない。
ウエイターにコーヒーを注文し、何となく周りを見渡してみる。
ラウンジの壁には誰のものかも分からない絵が飾られていて、床はピカピカに磨かれていた。
「お待たせ致しました。ごゆっくりどうぞ。」
ウエイターがコーヒーを置いて去っていく。
時計を確認すると待ち合わせの時間10分前だ。
コーヒーを飲もうとカップを持った時、
スーツ姿の女性が会釈をしながら近づいて来た。
彼女は僕の目の前にやってくると申し訳なさそうにこう話した、
「お待たせしました。遅くなってすみません。」
「いえ、まだ待ち合わせの時間前ですし、気にしないで下さい。えっとお手紙は…」
「私が書きました。今日はお呼びたてして申し訳ありません。
あの…それで、来て頂いて申し訳ないのですが、
実は先日お話したイベントが急に中止になってしまいまして。」
「あ、そうなんですか。そうならそうと言って頂ければいいのに。」
「…そうなんですが、実は今お会いしているのは私の個人的な興味からなんです。
ご迷惑でしたか?」
「迷惑じゃないですよ。どうせ暇ですし。」
「本当ですか?よかった。」
彼女は本当に安心したように初めて笑顔を見せた。
それから我々は、そのままコーヒーを飲みながら話し続け
気がつくと3時間が経っていた。
彼女はイベント会社に勤めていて、音楽イベントを多数企画しているらしい。
話し方にはなんだか独特のリズムがあり、会話しながら妙にリラックスしている自分に気が付いた。
身なりにはとても手入れが行き届いていて、すぐに好感を持つことができた。
しっかりとして見えるが表情はまだ少しぎこちなく見えたので、24歳くらいかな…と思ったら
本当に彼女は5つ年上の24歳だった。
彼女が僕に手紙を出したいきさつはこうだ。
偶然関わったライブイベントの打ち合わせで音楽事務所に寄った時、
偶然僕の曲を新人開発担当のスタッフが聴いていて、たまたま聞こえて
その後全曲を最初から最後までじっくり聴いたらしい。
「なんかこうピンときたんです。上手く言えないけど情景をとてもうまく描いている、というか。
風景の唄って感じがして。」
とのことだ。
「えっと…それで、そのまま僕の音源をもらってきたんですか?」
「そうです。イベントに誘いたいって言って。その事務所はよく付き合いがあったし、
私のことも信用してくれていてテープとプロフィールを受け取ったんです。
彼はあなたの曲を”悪くないけど、個性が足りない”なんて言ってました。
全然分かってないと思います。」
「はぁ…ま、そうでしょうね。じゃなきゃ事務所から連絡来てるはずだし。才能ないんですよ。
それにもう昔の話ですから。」
「昔の話?じゃ今は歌ってないんですか?」
「はい。今は普通に働いてますよ。」
「そんな…まだあなた19歳でしょう?あなたは絶対歌を歌うべきです。」
「そうでしょうか、でも現実的に…」
僕の言葉を遮り彼女は話す。
「今度の日曜日空いてますか?」
「あ、はい。」
「じゃ私に付き合って下さい。音楽の素晴らしさを再確認しに行きましょう。
とりあえずまた連絡します。」
そこまで言うと彼女はテーブルの伝票を手に取り、立ち上がった。
「あ、ちょっと…」
慌てて僕も後を追う。
彼女は勘定をまとめて払った。
「払いますよ。」
「いいんです。私がお願いして来てもらったんだから。では日曜日に。」
言い放つと笑顔を浮かべて、彼女は行ってしまった。
ホテルのロビーに一人残された僕は訳が分からなかった。
”一体なんなんだ…音楽の素晴らしさを再確認って…変わった人だ。
歌をやめてると話した途端に雰囲気が変わった。何だかちょっと気をつけた方がいいかも…”
そんなことを一人考えていた。
土曜日の夜、知らない携帯電話から着信があった。
あの時の彼女からだ。
結局、日曜日会うことになって待ち合わせ場所と時間を決めると
すぐに電話を切る。
日曜日、彼女は驚くべきことに昼から夜にかけて
ありとあらゆるライブハウスを廻る予定を組んでいた。
JAZZ、BOSSA NOVA、SOUL、と様々なジャンルに触れ
久々の生演奏に耳を傾けた。
一通り終わって、六本木のレストランへ入る。
カジュアルだが高級感があり、
サービスも味も申し分ない良い店だった。
「良い店ですね。」
僕が話しかけると、彼女は嬉しそうに話す。
「気に入ったならよかった。
この店は友達とも来れるし、打ち合わせにも使えるからよく来るの。
今日はかなり廻ったから疲ちゃったかな?」
「いや、大丈夫です。
こんなに一日でたくさんのLIVEに行くのは初めてでしたが。」
「良い演奏には、その場の空気を変える力があると思わない?」
「確かに。そうかもしれないですね。」
「ところで、」
彼女は一呼吸置いて言う。
「そろそろ敬語はやめましょう。
私はあなたより5つ上だけど、5つくらい大して変わらないでしょ?」
そこまで言われてから、
今日彼女が全く敬語を使わなくなっていたことに気が付いた。
僕は黙って頷いた。
レストランを出て、
「ここから歩いてすぐのところに住んでるの。
けっこう色々なレコードが揃ってるから、今度一緒に聴きましょうよ。
あなたがまた歌いたくなるように。」
そのまま彼女と別れ、家に帰る。
僕は自分に足りなかったものにやっと気が付いた。
今日一日で音楽をやっていた頃の心の震えを思い出すことができ、
そしてこの心の震えの理由は音楽だけではなかった。
それからはどちらから誘うでもなく
彼女と会う時間は次第に増えていった。
季節は秋も終わり、冬になろうとしている。
奇妙な出会いではあったけれど、僕は会う度彼女に惹かれていった。
彼女も、より感情を出すようになっていた。
ちょっとした仕草や、大人げない頑固なところも魅力的に感じていた。
そのまま月日は流れ、僕らはこのまま二人で上手くやっていけるんじゃないか
そう思っていた。
…でも結局のところ僕らはどこへも行けなかった。
彼女は、ある朝
やけに遠い目をしてこう言った。
「私ね、時々何もかもが分からなくなって逃げ出したくなるのよ。」
「誰だって多かれ少なかれ、そういう感情あると思うよ。もちろん僕にだってあるし。」
僕は励まそうと思いそう話すと、
彼女は下を向いて少し考えてから言った。
「あなたには分かってないのよ。」
その時僕は彼女をとても遠くに感じてしまっていた。
その話をした三日後、彼女とは連絡がとれなくなった。
携帯にかけると
「お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめのうえ…」
機械的なアナウンスが答える。
事務所の関係者も全く行方を知らなかった。
それどころか、住んでいたマンションは引き払ってしまっていたらしい。
何人かの関係者からはどこで調べたのか知らないが、
僕にまで電話をかけてきて彼女の行方を聞いてきたりもした。
彼女は消えてしまった。
その数ヶ月後
ポストを覗くと彼女からの手紙が入っている。
慌てて封を切ると
手紙はこう綴られていた。
「突然あなたの前からいなくなってすみません。
でも今の私にはこうすることしかできなかったことをどうか分かって下さい。
あなたに謝らなければいけないことがあります。
実は2年前あなたとよく似た声を持った人と付き合っていて、彼も当時歌を歌ってました。
でもあなたと同じように諦めてしまったんです。
私と彼は長い時間を共にしましたが、ある日何の便りもないまま私の前から消えてしまいました。
彼は歌を辞めてから、まるで別人のようになってしまっていました。
今となっては、生きているのかどうかさえ分かりません。
一番最初に事務所であなたの歌声を聴いた時、
もしかしたら彼かもしれないと思ったんです。でも違いました。
やっぱり、こんな話はするべきではなかったかもしれませんね。
本当にごめんなさい。
せめてあなたには歌を続けて欲しくて。
私はあなたに会う度、惹かれていきました。
でも私は彼を裏切ることだけはできないみたいです。
しばらくの間東京とは離れた遠い街で暮らすつもりです。
当時彼が私にしたことをあなたにしてしまっていることは、本当に申し訳なく思っています。
でも私にはどうすることもできませんでした。
私はあなたの歌がとても好きです。
あなたはきっと大丈夫だと思う。
また歌を歌って下さい。
きっと多くの人達に届くはずだから。
身勝手なことをして本当にごめんなさい。
短い間でしたが楽しかった。
素敵な時間をありがとう。
さようなら。」
喉の奥がカラカラに渇いて、上手く頭が回らない。
気がつくと真っ暗な部屋に僕はいた。
それからしばらくして会社を辞めた。
これからどう生きていくかは
もう決めていた。
最初の作品のタイトルは
彼女が言ってくれた
「風景の唄」
にしようと思う。
僕はそっと息を吸い込み、人波の中を一人歩き始めた。

萩原大介(ハギワラダイスケ )切ないメロディーで心の音を鳴らす孤高の唄い人。 「風景の唄」「希望の唄」「夕凪の唄」アルバム3枚全国リリース。 FMaiai毎週金曜日12時〜番組パーソナリティ。 歌を歌いながら文章を書いています。 blog毎日更新。 短編小説は不定期に新作をアップ。