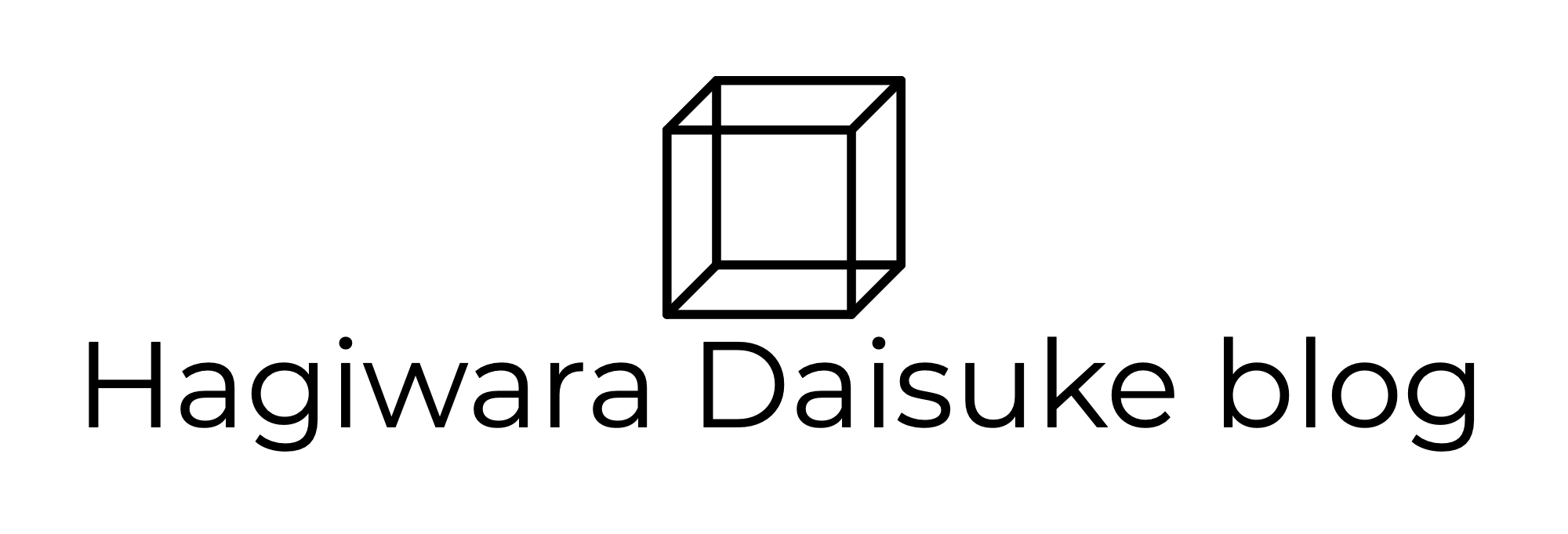僕らの生まれ育った町はどちらかと言えば田舎だと思う。
海と山に囲まれた小さな町だ。
自然の中で僕らは育った。今思うと良い環境だったと思う。
当時よく遊んだ友達のことを思い出す。
彼は見慣れた笑顔をいつも僕に向けていた。
1988年夏
家から小学校まで歩いて約20分。
授業が終わった後は走って帰り、鞄を置いてすぐに遊びに出かけた。
いつもの友達と一緒に。
学校のチャイムが鳴り、クラスメイトは話ながら帰り支度を始める。
誰かが帰り際に声をかけてくる。
「聖二、行こうぜ!」
友達の福田義人だ。
僕は彼のことを よっちゃん と呼んでいた。
「うん。行こう!」
よっちゃんは良いやつだ。
僕はどちらかと言うと人見知りで、友達と呼べる仲間はほとんどいなかった。
そんな僕に優しく声をかけてくれた。
今となっては基本二人で行動することがほとんどだ。
後で気付いたことだけれど、彼は僕と共通点が多い。
まずは、僕と同じで一人っ子。
団体で遊ぶことを好まず、家に篭ってゲームをすることも嫌いだった。
僕らは二人でサッカーやキャッチボールをしたり学校の裏山を探検したりして、
毎日泥まみれになって遊んでいたものだ。
よっちゃんはある日遠くを見ながら言った。
「それにしても、家でゲームなんかして何が面白いんかね?
俺からしてみたら意味分からんよ。」
「確かに。でも彼らからすれば、僕らの遊び方の意味が分からないんじゃないかな?」
僕がそう言い返すと、笑いながら応える。
「ハハ、そうかもな。俺ら二人は変わり者同士ってとこか。」
「そういうことかも。」
僕もつられて笑う。一通り笑った後、真剣な顔で言った。
「でも誠がいてくれて本当よかったよ。俺は一人じゃないからな。」
急に真剣な話をしている横顔はなぜか少し寂しそうに見えた。
気のせいかと思ったけれど、
後々それは気のせいではなかったことに僕は気付かれされることになる。
よっちゃんと遊ばない日は一人きりマンションの最上階へ登り、
空を見上げて雲の流れを目で追った。
まるで雲の向こうにとてつもなく大きな何かがあるような、
そんな想像をよく膨らましていたものだ。
あの雲の向こうには何があるんだろう?
何時間も青い空と雲を眺めていた。
実のところもう一つ密かな楽しみがあった。
歩いて5分の距離にある公園で星を見ることだ。
夜な夜な出かけて僕は一人空を見上げていた。
今日もいつものように公園へ向かう。
夏の夜風は少しべたつくが明日の朝へ向けて休憩をしてるような、そんな感じがして好きだ。
少し歩くといつものブランコが見えてくる。
今日のブランコには誰か座っていた。
この公園はマイナーな小さい公園で、今まで一度も誰かと会ったことはなかった。
今日は諦めて帰ろうかと考え始めたら、ブランコに座る人影に見覚えがあることに気付く。
人影はブランコを降りて、僕の方を見る。
「あれ?聖二、何でここにいるんだ?」
ブランコに座っていたのはよっちゃんだった。
安心した僕は思わず笑顔になり、言葉を返す。
「それはこっちのセリフだよ。びっくりしたぁ。こんな時間にどうしたの?」
少し気まずそうに頭をかきながら言った。
「いや…まぁ色々あってな。誠は?」
「一人でよく星を見に来てるんだよ。
とはいっても星座のことなんて何も知らないんだけどね…」
誰かに話すのは恥ずかしかったが、打ち明けるとよっちゃんは笑顔で言った。
「誠はロマンチストだな。今日は俺もお邪魔していいか?」
「もちろん!お邪魔してるのはこっちかもしれないしね。」
そう言いながら二人で少し笑った。
僕らは二人でブランコに揺られながら星を見上げる。
それから、よっちゃんと一緒に星を見るようになっていった。
遠くをぼんやりと見つめる姿は、どこか寂しさが漂っていたが
僕らはいつも同じようによく笑い。そしてよく遊んだ。
そんなある夜。
でかい紙袋を持って公園にやってきた。
僕の姿を見つけ笑顔になる。
「今日は遅めだね。」
僕は声をかけた。
「今日はプレゼントがあるんだ。」
大きい紙袋を僕に差し出した。
「ん?何?」
「まぁ、早めの誕生日プレゼントってことで。」
「誕生日は過ぎたばかりだけど。」
「ん~、じゃクリスマスプレゼント!
ってか何でもいいから開けてみ。」
「よく分からないけど、ありがとう!」
紙袋を開け、明らかに自分で包装したプレゼントを出してみる。
丁寧に包装をはがす。
「あ!こりゃ凄い!」
図式の星座早見表が入っていた。
丸い形になっていて回すと
季節ごとに見える星座を調べることができる。
「よかった!それ凄いだろ?これで星座の勉強しようぜ」
「いいね~ありがとう!よっちゃんから勉強って言葉が出るとはね。」
「確かに、初めて言った気がするよ。」
僕らは二人笑いながら、今の季節に合わせ星座を目で追っていった。
家に帰ってからも、一人で星座早見表を眺めていた。
肉眼ではかなり見えにくい星にもきちんとした名前があることに感心していた。
明日見たい星の方角を確認する。
翌日も、公園でいつものように星を見ていた。
足音がしたのでよっちゃんが来たと思い振り返る。
足音の主は見知らぬ二人組だ。
一人は茶色い長髪。
もう一人は帽子を深く被り顔がよく見えない。
いかにも悪そうな雰囲気だ。
そう思った直後二人は僕に向かって来た。
「お前ちょっと来いや。」
僕は腕を引っ張られ遊具の影に連れて来られた。
長髪の男が顔を近づけて話しかけてくる。
「金貸してくんねぇかなぁ。」
僕は目をふせて何とか言葉を返した。
「持ってないよ。」
「持ってねぇわけねぇだろが!いいから金出せ。」
帽子の男が怒鳴りつけてくる。
歯を食いしばりどうするべきか考えていたら、突然帽子の男が叫んだ。
「っ痛ぇ!」
頭を抱えて俯いている。見ると血が流れていた。
「おい…大丈夫か?このクソガキ!」
暗闇から現れたのは、よっちゃんだった。
見ると血に染まった石が落ちている。
長髪の男が向かった瞬間、腹を思い切り殴りつけた。
くの字に曲がった長髪の男の
足を強く蹴り上げ、顔面に拳をぶつける。
「どうした?クソガキに負けてるぜ。」
よっちゃんは倒れる不良をさらに蹴り続けた。
「よっちゃん、もういいって!」
僕が慌てて声をかけると、急に我にかえったように振り返った。
「大丈夫か?」
「大丈夫だけど…何もそこまでしなくても。」
「やられっぱなしじゃムカつくだろ。こんなクズはボコられて、なんぼなんだよ。」
さらに蹴りを入れる。
「ほらゴミども、さっさと失せろ。おうちに帰んな。」
唾を吐いて、よっちゃんは不良に言った。
頭を抱えていた帽子の男は、
長髪の男を抱えるように出て行く。
「何だか疲れたな…今日は帰るか」
「そうだね…帰ろう。」
帰り道、いつもの道をたどる。
「よっちゃん。」
「ん?」
「ありがとう。」
「何言ってんだ。助けんのは当たり前だろ俺たちは友達なんだ。」
僕らは肩を並べて、暗い夜道を歩いた。
それからというもの
しばらくの間、公園には行かなくかなってしまった。
不良グループにまた絡まれたくはなかったから、
というのが一番の理由ではあるけど何となく自分の習慣が変わりつつあることを感じてもいた。
それと同時によっちゃんともあまり遊ばなくなっていった。
最近の彼はいつもイライラしているように見える。
何回か声をかけたが、素っ気ない言葉が返ってくるだけだ。
どうしたものか…いつも考えてはいたが、
僕はいつの間にか他の友達と親しく遊ぶようになっていった。
しばらく経ったある日担任の先生は言った。
「今日は残念な報告があります。福田君がお家の事情で転校することになりました。」
クラスはざわざわしたが、よっちゃんは表情を全く変えず前を見つめていた。
でもその目はどこも見ていないように感じてしまった。
僕は帰り慌てて声をかける。
「よっちゃん、」
「ん?」
「転校するの?」
「あぁ…まあそういうことだ。」
「何で言ってくれなかったんだよ?」
「ごめんごめん。何だか言い出せなくてな。うちの父ちゃんと母ちゃん、離婚するんだとよ。」
「…え、離婚」
「大人は勝手だよな本当。ずっと仲悪くてついに爆発した感じかな。
でどっちについて行ってもいいって言われてな。
どっちでもいいって言葉が頭にきたから、俺はどっちにもついては行かないことにした。」
「そんな…じゃこれからどうするの?」
「東京に昔から世話になってる叔父さんがいるから、そこの世話になることにしたよ。」
「東京かぁ…寂しいな。」
僕が暗い顔をすると、彼は言葉を返す。
「まぁまたどっかで会えるだろう。大丈夫大丈夫。それに誠は上手くやっていける。
周りの人間を惹きつける魅力があるんだよ。俺の思った通りだ。」
懐かしい笑顔をつくって、僕の肩をポンポンと叩いた。
「まさか…わざと避けてたの?」
「まあな、前のままじゃ誠は一人になっちまうだろ?俺は浮いてるしなぁ。」
その瞬間に思ったことがあった。
両親の関係が良くなかったことから、人一倍孤独を感じてきたんだろう。
僕が孤独にならないように気遣かってくれていたんだ…
そう考え出すと
悲しさと寂しさで胸が苦しくなった。
「…いつ引っ越すの?」
「学校は今日まで、引っ越しは明日だ。」
「明日…随分急だね。」
「早く言うと何だか気まずいだろ?」
それから僕らは久しぶりに二人で帰り、
言葉少なに歩き、別れた。
翌日、僕はよっちゃんを見送るために彼の家まで行った。
叔父さんらしき人と荷物を積み込んでいる。
「お!来てくれたのか。そろそろ行くとこだよ。」
僕は慌てて紙袋を渡した。
「あ、ちょっと待って。これを。」
よっちゃんは驚きながら受け取る。
「ん?プレゼントか?」
「誕生日か、クリスマスプレゼントか、そんなところで。」
僕が言うとよっちゃんは笑顔になって、包装紙を開けた。
中には僕が買ってきた、星座の早見表が入っている。
「ありがとう。これで俺達は離れてても同じ星を見れるな!大事にするよ。」
そのまま手を振って、彼は車に乗り込み、
窓から顔を出して言った。
「また絶対会おうな」
僕は何度も強く頷きながら、車が見えなくなるまで手を振った。
涙が止まらなかった。
それから僕は、周りの友達とそれなりの距離を保ちながら残りの学生生活を送った。
よっちゃんのいない生活は味気なく、確実に何かが欠けている。
高校生活の中、僕は東京の大学に進学することに決めた。
18歳の春に僕は地元を旅立った。
新しい生活が始まり、僕は少しづつ東京に馴染んでいく。
ただ、心に空いた穴は埋まることがなかった。
夜の公園で空を見上げてみる。
”よっちゃん、東京の街ではあんまり星が見えないね。
”心の中でつぶやき、家に帰ろうと立ち上がる。
「東京ではあんまり星が見えないなぁ。」
誰かの声がする。
聞き慣れた、懐かしい声。
振り返ると、
星座の早見表をひらひらさせて誰かが僕に手を振っている。
よっちゃんだった
「よっちゃん?」
「久しぶり!」
久しぶりに会う彼は、笑ってしまう位変わってなくて口調も当時のままだ。
「何で?」
「何でって、俺は東京にいるって知ってるだろ?」
「いやそうだけど…」
よっちゃんは笑顔で僕を見て言った。
「本当は、偶然誠の友達が俺の知り合いだったんだよ。まさか東京で再会できるとはな。」
よっちゃんは嬉しそうに笑った。
まだ小さい頃見てた風景は、もう二度と見れない気がしてた。
でもそれは違ってたんだ。
僕らは二人で東京の空をいつまでも見上げていた。

萩原大介(ハギワラダイスケ )切ないメロディーで心の音を鳴らす孤高の唄い人。 「風景の唄」「希望の唄」「夕凪の唄」アルバム3枚全国リリース。 FMaiai毎週金曜日12時〜番組パーソナリティ。 歌を歌いながら文章を書いています。 blog毎日更新。 短編小説は不定期に新作をアップ。