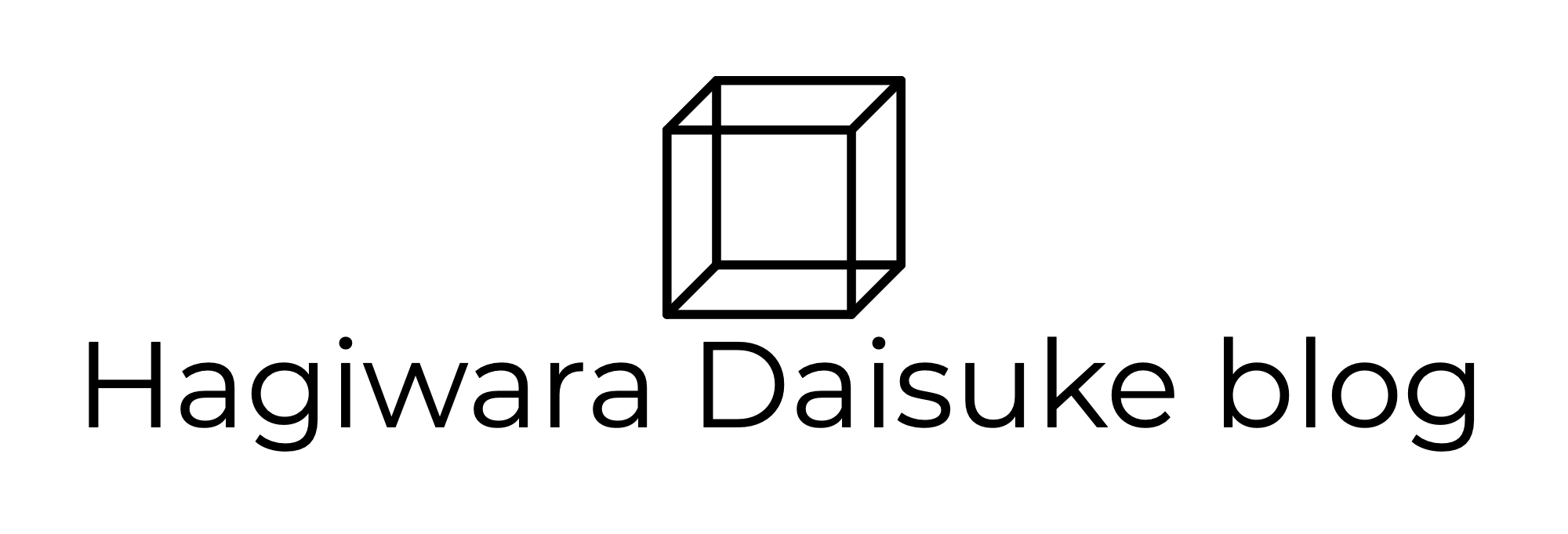1999年4月 東京 渋谷
雑踏の中、僕は1人歩いている。
18歳になってすぐ僕は東京にやってきた。
専門学校に通いながらの1人暮らしだ。
1人でいることは嫌いではなかったので、生活にはすぐに慣れていった。
まずはアルバイトを探そうと、街中を歩き回る。
店頭にアルバイト、パート募集と貼紙のある店をいくつかピックアップし帰宅した。
一人暮らしには慣れたものの、やはり渋谷の雑踏にはなかなか馴染めない。
暮らし始めの頃、道を歩いてるだけで行列になってしまう程の人には度肝を抜かれたものだ。
程なくして、アルバイト先を渋谷の駅近くにある喫茶店に決めた。
懐かしい感じの内装。
雰囲気が好きな感じだったし、サイフォンで煎れる本格的なコーヒーも魅力的だった。
学校に通いながら、夕方から夜にかけてアルバイトを続ける。
仕事に慣れ始めたある日、店の扉が開き男女4人組の団体が入ってきた。
僕は笑顔で声をかける。
「いらっしゃいませ。何名様ですか?」
「4人。見りゃ分かんだろ。」
目も合わさずに話す男の態度に内心ムッとしながら、奥の4名席を案内する。
空気を察したのか、先輩がオーダーを取りに行き客の対応をしてくれた。
しばらくしてから、
団体の中にいる女の子に見覚えがあるような
…そんな気がしてきた。
派手な雰囲気の連中だが、
1人清潔感のあるショートカットの女の子。
つい気になって、何となく目を向けると目が合ってしまう。
僕は慌てて目を背ける。
気になると人の目を見すぎてしまう、そんな癖が僕にはあった。
しばらくの間、黙々と仕事をしていたら
さっき目が合った女の子が僕に話しかけてくる。
「ねぇ、佐原君よね?」
僕は内心びっくりして飛び上がりそうだったが、気持ちをおさえながら振り返る。
「そう、ですけど。」
目が合った瞬間、彼女は嬉しそうに返した。
「やっぱり!私のこと覚えてない?」
「…えっと」
そう、確かに見覚えはあるんだが
どこで会ったかは思い出せなかった。
「ひどいわねぇ。ま、一度も話したことないからしょうがないわよ。
私達同じ高校に行ってたのよ。」
言われてから、思いつきで聞いてみた。
「もしかして、片平の彼女…?」
「そう。とっくに別れたけどね。」
彼女は苦笑いを浮かべながら言った後、申し訳なさそうに続ける。
「ごめんね。うちの連れ、感じ悪かったよね…」
僕は自分の気持ちを見抜かれたことが恥ずかしくなって慌てて話した。
「あ、いや全然気にしてないよ。僕も飲食店の店員に気を使ったりしないし。」
「あの連中ね、悪い人達じゃないけど。気遣いが本当足りないのよ。」
やれやれ といったジェスチャーで彼女は話した。
彼女が片平と別れた原因は、確か片平の浮気だった。
「俺は同時に何人もの女を愛せる男だ。
それを理解してもらえなかったから今の彼女とは別れる。」
というのが友人である片平の言い分だった。
はっきり言って無茶苦茶だが、まぁ価値観は人それぞれだから仕方ない。
会話の流れが難しくなってきたので僕は席に戻るよう勧める。
「一緒にいる人、彼氏でしょ?そろそろ戻った方がいいよ。」
「違うよ~あたしはあんなのとは付き合わない。
片平君と別れて以来、男の人はあんまり信用しないことにしてるの。」
真顔で僕に言葉を返した。
「そっか。」
僕は少し気まずくなり笑顔で返す。
「でも佐原君なら信じてもいいかもなぁ。
片平君と付き合ってる頃、あの人佐原君の話ばっかりしてたのよ。あいつは本当良い奴だって。」
彼女は笑顔で話した。
「まぁ、長い付き合いだったしね。」
僕が彼女に話した後すぐに奥のテーブルにいた他の三人がこっちに向かってくる。
「美穂、そろそろ行こう。お勘定よろしく。」
彼女と一緒にいた女の子が伝票を僕に渡してきた。
後ろから他の男二人もついて来る。
「ありがとうございます。」
レジのある出口へ向かう僕の後ろから、話し声が聞こえてくる。
「急にいなくなったから心配したわよ。あの店員知り合いなの?」
「知り合いではあったけど、初めて話したの。」
「何それ?変なのー」
そのまま会計を済ませる。
帰り際、彼女は僕を見て言った。
「あ、私の名前は上田美穂。よろしくね。」
僕も慌てて自己紹介する。
「佐原浩二です。こちらこそ、よろしく。」
手を振りながら彼女は帰っていった。
彼女達が帰った後、
テーブルを片付けながら片平のことを思い出していた。
片平は高校時代によく遊んでいた友達で、
女性にはだらしなかったがよく気の利く良いやつだった。
今思うとモテなかった僕に比べ、片平がモテたのも分かる気がする。
ハッキリ言って見た目はそれほどではないんだが、とにかく明るくて運動神経が抜群だった。
学生時代というのは、運動神経が良い男がモテるものだ。
僕は当時から、どちらかと言えば地味で目立たなかったので
そんな僕と片平が仲良かったのは今でも奇跡だと思っている。
まぁそれより、片平の彼女だった上田美穂と東京でばったり会うことの方が奇跡かもしれない。
それから彼女は僕がアルバイトで店にいるとき、よく客として来るようになった。
女友達と来ることが多かったが時々1人でもコーヒーを飲みに来ていた。
店は基本的に暇な時間の方が多かったので
彼女が一人で来ている時はよく他愛のない話をしていたものだ。
天気の話や、最近聴いている音楽、テレビ番組の話等、
言ってしまえば本当にどうでもいい類いの話。
プライベートな質問をすると彼女はいつも笑顔を浮かべてこう言った。
「まぁ…私のことはいいじゃない。」
”プライベートな話はしたくない”
という意味として僕は受け止め、僕は彼女と接した。
そんな日がしばらく続き、季節は夏になり、やがて秋が通り過ぎて冬がやってきた。
時間の流れというのは本当に早いものだ。
ある日、彼女はいつものように店にやって来てこう言った。
「佐原君、ちょっと相談があるんだけど。今日バイトの後で会えないかな?」
いつも通りの笑顔を浮かべてはいたがその表情はどこかいつもとは違っていた。
アルバイトの後、特別な用事なんてなかった僕は彼女に話す。
「大丈夫だよ。ただバイト終わるの23時だから、遅いけど。」「じゃそのくらいにまた来るね。」
そう言い残して、店を出ていく。
実のところ僕はドキドキしてしまっていた。
いつからか僕は、彼女に惹かれてしまっていたからだ。
上の空で、閉店後店を出ると彼女は店の前で待っていた。
僕の姿に気付くと彼女は笑顔で手を振った。
僕は急いで声をかける。
「ごめんね。店の中で待っててもよかったのに。」
僕が彼女に言うと、少し微笑んで言葉を返した。
「謝ることないよ。私がお願いして勝手に待ってただけだから。ついて来てくれる?」
言い終えると彼女は歩き始めた。
しばらく歩き、何の迷いもなく彼女は深夜営業のBARへ入っていった。僕も後を追う。
店に入るとオールバックで髪をまとめたバーテンダーが声をかける。
「いらっしゃいませ。」
彼女は表情を全く変えず言った。
「2人。奥の席空いてる?」
様子からして初めて入る店ではないことが分かる。バーテンダーは笑顔で言葉を返す。
「はい。空いています。どうぞ。」案内され、僕らは席につく。
僕はビールを彼女はウォッカトニックを注文した。
オーダーが来てから彼女は話始めた。
「あの…変なお願いなんだけど、もしよかったら佐原君に私の恋人役をやって欲しいの。」
「恋人役?」
思わず聞き返した僕を見て、彼女は俯きながら頷いた。
「やっぱりこんなお願いおかしいよね…」
僕は慌てて笑顔で返した。
「あ、いや、とりあえず話を聞かないと何とも言えないかな。」
少し安心した表情で彼女は話し始める。
彼女がこんな話をしてきた理由はこうだ。
彼女は同じ大学に通う男から告白され、「結婚したい」とまで言い寄られている。
何度も断ったがしつこくて、いつまでもあきらめてくれない。
最近ではストーカーまがいのことまでしてくる。
恋人がちゃんといて、もう無駄だと思わせたい。
…という話。
話を聞き終えた僕は、
”まずいなぁ。この空気は断れない。場合によっちゃその男に刺されるかも…”
そう思ったものの、気が付くともう1人の自分が声を出していた。
「分かった。力になるよ。」
その瞬間、彼女は心から安心した表情で言った
「本当?ありがとう!やっぱり佐原君に相談してよかった!」
”恋人役か…”
もう1人の自分に負けた僕は正直複雑な気持ちだったが、
彼女の気を使った表情を見ると何も言えなかった。
話が落ち着いた後、お金を払おうとする彼女から伝票を奪い会計を済ませる。
「もうちょっと飲もうよ。」
そう言う彼女を説得し、翌日会う約束をした後彼女が終電に乗れるよう帰した。
例の男が気になったが、今日は大丈夫とのことで渋谷駅改札で彼女を見送る。
改札で手を振った後、自分の終電がなくなっていることに気付く。
溜息をつきながら2時間の距離を歩いた。
翌日、作戦会議
例の男に僕の存在を知らせるため2日おきに彼女と会うように時間を合わせた。
あくまで、恋人という設定なので基本歩く時は手を繋いだ。
段々、自分が何をしてるのか分からなくなっていたがそんな環境に喜びを感じている自分もいた。
並んで歩く彼女の横顔は、本当に魅力的だった。
そんな生活が続いたある日。
バイト終わりの帰り道。疲れた体を冬の夜風が包み込む。
真っ直ぐ家路を急いでいると、ポケットの中にある携帯が鳴った。
珍しく、片平からだった。
「もしもし。」
「あ、いきなりごめんな。今大丈夫か?」
片平と話すのは2年振りくらいだろうか…
謝ってる割に堂々とした話し方が懐かしい。
「大丈夫だよ。久しぶり!」
「あぁ本当に。元気か?東京はどう?」
「親父みたいな聞き方すんなって。元気にやってるよ。」
「そっか。ならいいんだけど。こっちは相変わらずだよ。」
「また彼女いっぱい作ってんの?」
「お前な、人聞き悪いこと言うな。まぁその辺も変わりないけどな。」
全く悪びれた様子もなく言う。
僕は溜息をついて、上田美穂のことを切り出してみた。
「その人気者のお前が前に付き合った女の子と、東京で再会したよ。」
「マジか?誰だ?」
「上田美穂さんって覚えてる?」
「上田美穂?上田…、そんな名前の女と付き合ったことないぞ?」
「おい。付き合った人の名前まで忘れたのか?」
「いや、俺は女の名前を忘れたりはしない。その女、偽名を使ってるんじゃないか?」
「何のために?」
「それは知らん。まぁとにかくちょっと変だな。気をつけろよ。
あ、お前が変な話するから用事を忘れそうだった。来週東京行くんだけど、泊めてくれるか?」
「それは構わないけど。」
「じゃその女の話は会った時にな。じゃ。」
電話が切れる。
片平の性格はまるで変わっていなかった。ただ、そんなことより、彼女のことだ。
胸の奥にぽっかり穴が空いたようだった。
彼女は何者なんだ?
片平のそんな話の後も、僕は変わりなく彼女と接した。
本当のことを聞き出したかったが、どうしても聞くことができず1週間が過ぎる。
片平が東京に来る日。
僕は東京駅まで迎えに行くことになっていた。
改札に立っていると手を振っている片平が見えた。
僕も手を振り返す。
僕の肩に軽く拳を当て嬉しそうに言う。
「久しぶり~!迎え来てもらって悪いな。」
「気にしなくていいよ。今日は休みだし。」
そのまま僕の家へ連れて帰り、お互いの近況を話していた。
ふいに上田美穂の話になる。
「そういえば、あの女どうした?ほら上田とかいった。」
「何も変わりないよ。結局まだ詳しく話しもできてなくて。」
「そうか。写真ある?」
「1枚だけある。」
「見せてくれ。」
僕は携帯のカメラで撮った写真を見せた。
真剣な顔で写真を見た片平は、無言で携帯を僕に返す。
「やっぱり俺はこの女のこと知らないぞ。」
「え?でも高校の時一緒にいるところ見た気がしたんだけど。」
「誰かと見間違えたんだろう。
女って制服のせいもあるが、髪型が同じだったりするとよく似て見えるもんだ。
自分の記憶に確信持てるか?」
「言われてみれば、確信は持てないかも…」
彼女があまりにも自然に話しかけてきたからだろうか。
疑ったことはなかった。
ただ、片平の目を見ると嘘でないことは明らかだった。
翌日はバイトだったので、片平には好きに過ごしてもらうように家のスペアキーを渡した。
彼女が店に来たら…と思うと落ち着かなかったが幸いその日は現れなかった。無事バイトを終える。
帰り道、考え事をしながら歩いていた。
一体彼女の目的は何だ?
どこからが嘘でどこからが真実なんだ?
色々考えていたせいで、人影が僕の横を通り過ぎたことにすぐに気付けなかった。
その人影を見た瞬間、僕は無理矢理に路地裏へ引っ張り込まれた。
暗い道で顔は見えないが、肩幅のしっかりとした男だ。
見覚えはない。
男はイライラした様子で話した。
「てめぇ人の女に手出してんじゃねぇよ。」
言い終えた途端、拳が僕の腹にめりこむ。
僕が倒れ込んだところを男はひたすら蹴り続けた。
僕は訳も分からず、薄れかけた意識の中で思った。
”ストーカーの話は本当だった。じゃどっからが嘘なんだ?…”
痛みはあまり感じず、僕は彼女のことを考えていた。
しばらくして、急に男の動きが止まる。
「何だお前。」
男が誰かと話している。
「おい!大丈夫か?」
朦朧とする意識の中、片平の声がする。
そのまま僕は気を失った。
目が覚めると僕は病院にいた。
「あれ…」
「お、目が覚めたか。」
片平がすぐに医者を連れて来る。
しばらく診察してもらい医者は言った。
「もう大丈夫でしょう。安静にして、あと2、3日は入院して下さい。」
僕に微笑みかけ出て行った。
片平は安心した表情で溜息をつく。
「心配かけやがって。」
僕はストーカーの男を思い出し尋ねた。
「そういえば…あいつは?」
「ん?あ、ストーカーのガキか?警察に突き出した。帰りがあんまり遅いから迎えに行ったんだ。
見つけてよかったよ。おい、そろそろ入って来なよ。」
片平は病室の外に向かって言った。扉が開き、入ってきたのは上田美穂だった。
俯きがちに僕の顔を見る。「佐原君、本当にごめんなさい。」
彼女は涙ぐんでいた。何も言葉にならない彼女の代わりに片平が話し始めた。
「佐原、お前3日間眠り続けたんだよ。
その間お前の家にお邪魔してて、彼女が訪ねてきたってわけ。」
「3日間?ヤバい!バイトが!」
僕は慌てて起き上がろうとするが、激痛が走る。
「いたたたた…」
僕の体を抑えながら片平が言う。
「お前本当に馬鹿みたいに真面目な奴だな。
心配しなくてもこの女に聞いてバイト先の店には事情話してあるよ。」
片平は、上田美穂を見て話し続けた。
「ほら、本当のこと話してやれよ。俺は君と付き合ったことなんてないぞ。」
僕も彼女を見て尋ねた。
「えっと、とりあえずどっからが本当でどっからが嘘か教えてくれる?」
まだ落ち着かない泣き声のまま、彼女はゆっくりと話し始めた。
「…ごめんなさい。騙すつもりはなかったんだけど。
同じ高校に通っていたことは本当で、私は一方的に佐原君と片平君を知ってたの。
佐原君を偶然見かけた時、優しそうだったから…。」
僕は、必死に自分を落ち着けながら言った。
「何も、嘘つかなくてもよかったのに。」
「そうだよね…ごめんなさい。」
聞き手に回っていた片平が声をかける。
「佐原、まぁ許してやれよ。
とりあえずストーカー野郎は彼女が話したいくつかの証拠とお前をボコったことで逮捕されたし。
君も申し訳ないと思うなら、退院するまで見舞に来てやれ。」彼女は黙って頷いた。
僕は複雑な感情に支配され、とにかく一人になりたかった。
「もう大丈夫だから、2人とも帰ってくれていいよ。ありがとう。
少し疲れた。それから上田さん、僕の役割は終わったんだよね?もう気を使わなくていいよ。」
僕が言った後、彼女は言葉を返す。
「…でも。」「本当に大丈夫。ちょっと1人になりたいから。」片平が彼女を連れて出て行く。
「明日また来るわ。ゆっくり休んでな。」
片平が言いながら病室の扉を閉める。それから2日後、僕は無事退院することができた。
片平は一度来てくれたがその後は来なくていいと伝え、
僕が退院したのを見届けた後で地元へ帰って行った。
彼女も何回か見舞に来てくれたが、謝ってくるばかりでほとんど会話もなかった。
退院後、僕はバイトと学校に復帰し元の生活を始めた。
彼女からの連絡は少しずつなくなっていった。
日々の中で時間が過ぎれば過ぎるほど、僕は逆に彼女のことを考えずにはいられなくなっていった。
行き場のない想いを抱え、最後にもう一度だけメールをしようと携帯電話を握りしめる。
「もしよかったら、2人で話をしない?」
メールをしてみた。
翌日返信があった。
「私も話したいです。」
僕は彼女の家に行くようメールで伝え、会いに行く。
会ってすぐに再確認してしまった。
分かってはいたことだが、彼女は僕のことを愛してなどいなかった。
泣き続ける彼女を慰めて、少し落ちついた後。
「佐原君みたいに美味しいコーヒーは用意できないけど、コーヒー飲む?」
「ありがとう。」
彼女のコーヒーは、何というかとても優しい味がした。
彼女はそっと窓際に向かいレースのカーテンをめくり、呟いた。
「雪が降ってきたよ。」
僕も窓際へ向かい外を見る。東京には綺麗な粉雪が降っていた。
少し話した後、僕は席を立つ。駅まで彼女は見送ってくれた。
「佐原君ともう少し早く出会えたらよかった。」
彼女は寂しそうに言った。
あぁこれで最後なんだ…
僕はただ孤独を噛み締めて、彼女を見た。
僕には何も言えなかった。
改札を入り振り返ると、雪景色の東京で白い息を吐きながら彼女は僕に手を振っていた。
僕は手を振り返さずに電車に乗り込む。
座席に腰掛け、僕は頭を抱えるように指でこめかみをおさえ1人で泣いた。
それから彼女とは完全に音信不通となった。
短い思い出と
雪の降る街で手を振っていた姿を
僕の記憶に焼き付けたまま。
2005年6月
僕は一人、久しぶりに渋谷の街を歩いている。
雑踏は何も変わっていない。
アルバイトしていたカフェはいつの間にかなくなってしまったようだ。
真新しいレストランになっていた。
晴れた空を見上げると、急に胸が軋むように痛み壊れそうになった。
痛みを耐え続け…
僕はただ…
いつもいつの日にも
彼女が笑っていられるように
そう心の中で祈り続けた。
いつまでも祈り続けた。

萩原大介(ハギワラダイスケ )切ないメロディーで心の音を鳴らす孤高の唄い人。 「風景の唄」「希望の唄」「夕凪の唄」アルバム3枚全国リリース。 FMaiai毎週金曜日12時〜番組パーソナリティ。 歌を歌いながら文章を書いています。 blog毎日更新。 短編小説は不定期に新作をアップ。