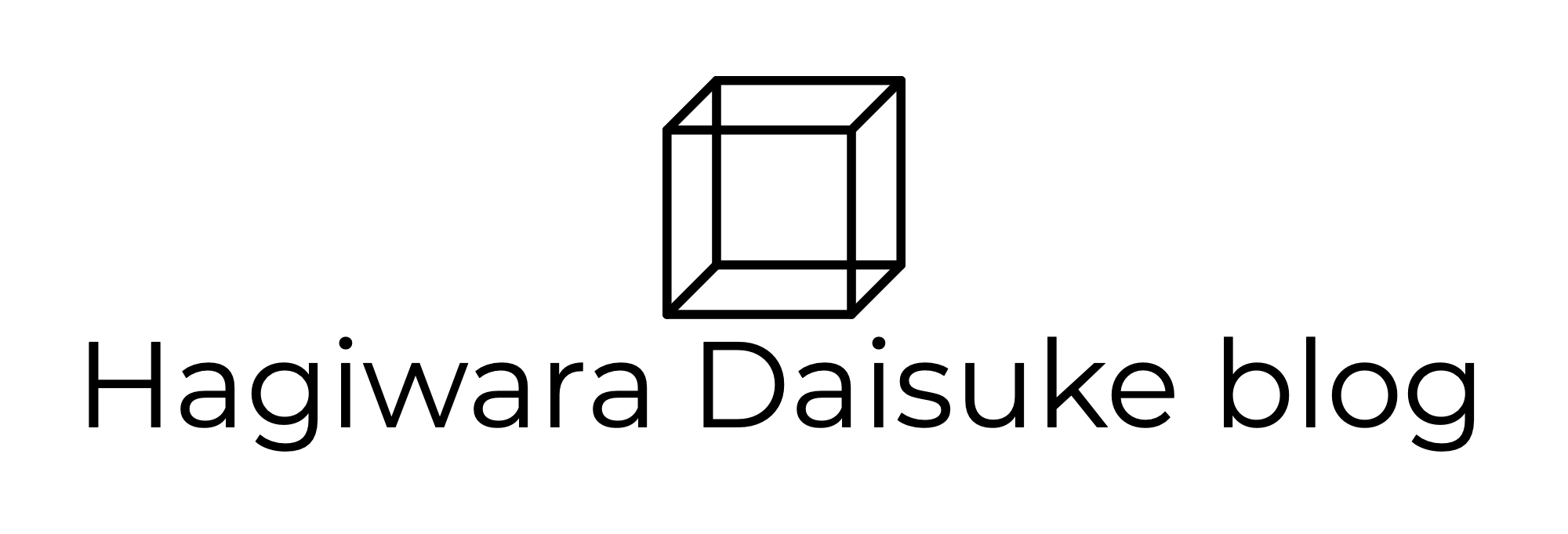朝、目が覚めた。
時計を見ると午前5時半を指している。
少し早いがまぁいい。
今日僕は旅に出ることに決めていた。
ゆっくり起きあがり、洗面所で歯磨きをしながら自分の顔を鏡で見
相変わらず酷い顔だ。
ぼやけた頭で考え事をしながらコーヒーを淹れる。
そう、僕はいつもうまくいかない。
不器用でお人好しを絵に描いたような人間で。
そんな自分にウンザリしてる。
結局のところ、そういうタイプの人間はいつも損をするし、孤独だ
何もかもが嫌になった僕は、仕事や人間関係その全てを一度リセッ
なけなしの現金と最低限の荷物をカバンにつめて旅に出ることにし
どこでもよかった。
ただ遠くへ行きたかった。
適当に調べたフェリーに乗り込み
11時間船に揺られた後、ある島に行き着いた。
船を降りて浜辺で座り込み
僕は一人海を見ている。
波の音が優しく聞こえていた。
こうして冷静になればなるほど、自分が自分でなくなるような、そ
悲しみはただ心に積もっていく。
そんな時、僕は悲しみが通り過ぎるのをひたすら耐えた。
今まで僕の身に起きた出来事を少し思い出してみようと思う。
2007年夏
僕は当時22歳、工事現場で日雇いのアルバイトをしていた。
「おい!何もたもたしてんだ。そんなペースじゃ日が暮れちまうぞ
現場の責任者が怒鳴る。
「はい。すみません。」
僕は伸びすぎた前髪を指でどけながら
上司に詫びた。
しかし、働けば働くほど、
“一体何してんだろう。こんなことしながら死んでいくんだろうか
そんなことを頭に浮かべていた。
僕には心を許せる友人も、
愛を語り合える恋人もいなかった。
やりたいことも特になくて
ただ時間を無駄にすり潰していた。
もちろん、過去に付き合った女性がいないわけではない。
だが僕らは出会って、しばらくした後
まともではいられなくなってしまった。
それは僕ではなく、”彼女が”
ということになる。
当時彼女には兄がいた。
両親とは仲が良くなかったが兄とは密に連絡を取り合う仲だった。
直接会ったことはないが、写真で見る限り魅力的な人のようだった
彼女も兄の話をするときは、決まって笑顔になっていたことを思い
ただ、彼は
ある日突然、この世からいなくなった。
用事を済ませて帰宅しようとしていた僕の携帯電話が鳴る。
見ると彼女からの着信だった。
「もしもし。」
「…お兄ちゃんが死んじゃった…」
「え?」
「今日ね、交通事故で…連絡があって。お兄ちゃんが、死んだって
彼女の声には生気というものが全く感じられなかった。
「分かった、後でまた連絡するから
とりあえず落ち着いて…」
そう話したところで急に電話は切れた。
その後はかけ直しても、しばらくの間繋がらなかった。
僕は、両親と仲が良いとは言えない。
しかしながら悪いわけでもない。
兄がいるが、兄も同じようなものである。
つまりは、僕は家族を亡くしたことがまだない。
その時の彼女の気持ちをどう受け止めていいのか、まるで分からな
でも全力で彼女を受け止めてあげたかった。
葬儀が終わり、しばらくしてからも
彼女は笑っていたかと思うと急に狂ったように泣き出したり
僕のことを執拗に罵倒したりすることもあった。
彼女の言い分はいつも、
「あなたには何も分かってない。やっぱり他人なんだね。」
という言葉だった。
僕はただ黙ってやり過ごすことしかできなかった。
何度か友人にこのことを話したが
「お前がそこまで落ち込む必要ないんじゃないの?」と言われたこ
この時に僕は”他人て、なんてよそよそしくて冷たいんだろう”
と強く思って落ち込んだものだ。
それからだろうか。
僕はずっと自分自身に悪いことが起こると、それが当たり前だと感
僕のような人間が幸せになってはいけない、そう強く思うようにな
彼女とはその後もしばらく付き合ったが、いつのまにか連絡を取ら
別れることになる。
現場の責任者に散々嫌味を言われながら
アルバイトを終え、家路につく。
嫌味を言われることに何も感じなくなっている自分に気がついた。
いつもヘラヘラと笑って済ませた。
コンビニで缶ビールを買って駅のホームで椅子に座りながら缶を開ける。
疲れた体にビールが染み込んでフワフワとしながら
色々と頭に巡
そのままボーッとしていたら誰かの声がする。
「何やってんの?」
顔を上げると高校時代の同級生が立っていた。
名前は確か…柴田弘。
同級生というだけで、ハッキリ言って自分としては友達とは思って
なんとなく言葉を返した。
「久しぶり、いやバイト終わりでね。」
驚いた様子で柴田は続けた。
「ん?ここらへんでバイトしてたんか?俺の家駅からすぐなんだけど、ちょっと来ない?
酒飲んでるくらいだから忙しくはないだろ?
柴田は、もう少しで空になりそうな僕の持ってるビールの缶を指差して言った。
正直面倒だったし疲れていたけど、特にやることもなかったので彼
「んー、じゃ行こうかな。」
そう返すと、少し笑顔で柴田は歩き出した。
ゆっくり立ち上がって後を追う。
家は本当に駅近だった。
2LDKのマンション、駅から5分。
アクセスの悪い家に住んでる僕は素直に驚いた。
「ここは便利だなー。家賃高いっしょ?」
「うーん、まぁぼちぼちかな。」
話を聞くと柴田は高校卒業してすぐに父親に資金を借りながら起業したらしく、
年収を聞くと泣きたくなった。
僕の年収よりゼロが2つ多かったのだ。
初のお宅訪問を終えて、ほろ酔いになりながらまた電車に乗って帰
それからは
頻繁に柴田から連絡が来るようになり、度々家にも遊びに行った。
そんなある日
僕とは違って女性付き合いが盛んならしく、
いつものように彼の家で話を聞いていた。
「それでさ、その女がね。…で本当ありえねぇんだわ。
何考えてん
柴田は少し苛立ちながら僕に声をかけていた。
「あ、ごめん。えっと、なんだっけ?」
僕はここ何日か誰といても頭が常にぼーっとしてしまっていて、
会話を聞き逃すことも増えていた。
「…お前なぁ最近おかしいぞ。いつもぼけっとしてる。何かあった
正直なところ、毎日ハードなアルバイトと酒漬けの日々で僕は自分
柴田は、心配と苛立ちを合わせたような表情で僕に話してさらに続
「実はな、お前に会わせたい人がいるんだ。これからここに来るか
僕は溜め息をつきながら言い返す。
「いきなり会わせたい人がいるってなに?女の子でも紹介しようっ
「いやいや、それはちょっと違うな。
まぁ確かに女性だからいずれ
なんとなく居心地が悪く感じたがそのまま話し続けて30分程経っ
「あ、来たかな」
柴田が立ち上がって玄関の鍵を開けた。
話の通り女性と共に柴田が部屋に戻ってくる。
ショートカットの小柄な女性で、あまり特徴のない顔立ちだった。
「紹介するよ。こちら上原美咲さん。
ウチの仕事をたまに手伝ってくれててね。
彼女も忙しい身だから、なかなか出会いがなくて誰かを紹介して欲
僕は軽く会釈をした。
彼女は僕の顔をじっと見ながら遠慮がちに話した。
「こんにちは。いきなりすみません。
この間柴田さんとお会いした時に色々お話してまして、
今日お伺い
自分が迷惑そうな顔してるような気がして僕は少し焦って答えた。
「あ、いやいや、そんなことないですよ。よろしくお願いします。
柴田が笑いながら続ける。
「堅いなぁ2人とも。まぁ楽しくやろう。」
その後は、彼女が合流する前の会話に戻り、柴田の他愛もない会話
彼女も打ち解けて敬語も使わない良い雰囲気で話していたものの、
柴田に言われて、彼女と僕は連絡先だけ交換してその場は解散とな
その数日後、僕は予想もしない形で彼女と再会することになった。
仕事終わりで駅へ向かう。
雨が降り出し、持っていたビニール傘をさした。
雨の日は嫌いじゃない。
なんというか、空気が感情を持ってるようなそんな気がするからだ
ICカードを取り出し、改札を入ろうとした時見覚えのあるシルエ
上原さんが外を見ながら憂鬱そうな表情で立っていた。
僕はそっと声をかける。
「こんにちは。あ、この間はどうも。」
彼女は最初驚いた表情で、その後少し笑顔を作って答えた。
「こんにちは!びっくりしたぁ。」
笑顔を見て安心した僕は続ける。
「誰かと待ち合わせ?」
「いや、そうじゃないんだけどね。少し雨が弱くなってから帰ろう
でも、変わらないね。」
そう言った後、少し困った表情で微笑む。
自分が折りたたみ傘を鞄に入れていることを思い出し伝える。
「傘、もう一つ持ってるからこれよかったら使って。」
僕は手にしていたビニール傘を彼女に手渡した。
「いいの?」
「全然大丈夫。」
「ありがとう。じゃまた連絡するね。その時に返します。」
彼女は少し微笑みながら言った。
それからは
ふとした時に彼女から連絡が来るようになった。
「たまにね、どうしてるかな?とか考えたりしちゃうんだよねぇ。
と、連絡が来たりすると
密かに僕はドキドキしていた。
ただ一つ気になることがあった。
彼女は、真夏の猛暑日でも絶対に長袖のシャツを着ていた。
最初は日焼けでも気にしているのかと思ったがなんとなくそれは違
何かを隠しているような、そんな仕草がたまに気になってしまった
ある日、
彼女の袖から腕にいくつかの傷を見かける。
彼女は慌てて袖を伸ばして傷を隠した。
触れてはいけないような気がして僕はそのことには特に触れなかっ
しばらくの間、傷については触れずにいたが彼女からその話をして
「実はね、私小さい頃からよく父に叩かれて。それが傷になって今
ずっと自分は産まれてきちゃいけない子なんだ
人は誰しも孤独だ。
それを埋めるために誰かを愛するんだろうか?
そして、その結果
最愛の人を傷つけることで自分の存在を示そうとする。
一体人の感情って何なのだろうか。
この日から僕はずっと答えの出ないこの問いを自分に何度も問いか
優しさというのは時に残酷だ。
彼女の話を聞いて僕はそう強く思った。
その後は、その話に触れることもなくなって僕達は同じ時間を何度
ある日一緒に出かけた帰り道、お互い酔っ払っていたこともあって
少し休もうと公園に寄った。
夜空を見上げて彼女は言う。
「あーあ、なんか色々めんどくさいよね。」
僕はすぐに言葉を返す。
「何かあったの?」
そう言うと彼女は少し微笑みながら
「大丈夫大丈夫。大したことじゃないから。」
僕はその言葉を鵜呑みにして、彼女の横顔をただ見ていた。
しばらく会うことがなくなっていたある日、彼女は遠い町へ引っ越
「寂しくなるなぁ。」
柴田がつぶやいた時、彼女は少し微笑んだだけで、何も言わなかっ
突然引っ越すことを告げられ、状況を飲み込めないままいた。
片付けも終わったところで柴田は「仕事があるから」と帰り支度を
「じゃ俺行くわ。上原さん、またね。こっち来ることあったらいつ
柴田は手を差し出して、彼女と握手をする。
「ありがとう。」
さっきと同じような寂しさを含んだ微笑みで彼女は言った。
柴田が帰った後、彼女は引っ越しの理由を話してくれた。
“一人暮らししてる間に両親が離婚し、母親が1人になってしまう
というのが概ねの筋書きだが、
同時にこう言った。
「父が私のところに来るかもしれなくて、何するか分からないから、
ここを離れることにしたの。」
「そっか…」
僕はそう返すことしかできなかった。
帰り際、駅まで送ってくれた。
「それじゃまたね。」
彼女はそう言って、僕は改札を入る。
振り返ると彼女は改札の向こうから笑顔で手を振っている。
僕も手を振った。
笑顔には…なれなかった。
本当は僕が彼女を守りたかった。
でも、その言葉が言えなかった。
いつからか、僕は彼女のことをとても愛してしまっていた。
それから数年後に柴田から彼女の話を聞くことになる。
“彼女はこの世からいなくなってしまった。”
と。
引っ越しの時には既に重篤な病にかかっていて、その後亡くなった
思えば時々、具合悪そうにしていた姿を見かけた。
いつも彼女は決まって「大丈夫だから」と微笑んで、
愚かな僕はそ
大丈夫なんかではなかった。
胸の奥に軋むような痛みを感じて
動けなかった。
“大切な人は突然、何の前触れもなくいなくなってしまうんだ”
その残酷な事実を痛感するしかなかった。
せめて僕は
本当の気持ちをきちんと彼女に伝えておくべきだった。
”愛している”
と伝えるべきだった。
その日、僕は夜通し泣いた。
人はここまで涙が出るものなのかと驚くほど泣き続け、
部屋の中の
彼女はもういない。
僕に微笑んでくれることもないのだ。
頭の中の彼女は改札の向こうから笑顔で手を振っていた。
あれが最後なんて思いもしなかった。
今、僕は小さな島で夜明けを迎える
少しずつ明るさを戻して。
太陽の光は確実に”今”を照らしている。
僕はただ、前を向いて歩き始めた。
大切な人との思い出を胸に。
“愛する人に愛してると伝えよう。
できる限り一緒にいよう。
時間を大切にしよう。”
そう強く心に刻みながら。

萩原大介(ハギワラダイスケ )切ないメロディーで心の音を鳴らす孤高の唄い人。 「風景の唄」「希望の唄」「夕凪の唄」アルバム3枚全国リリース。 FMaiai毎週金曜日12時〜番組パーソナリティ。 歌を歌いながら文章を書いています。 blog毎日更新。 短編小説は不定期に新作をアップ。