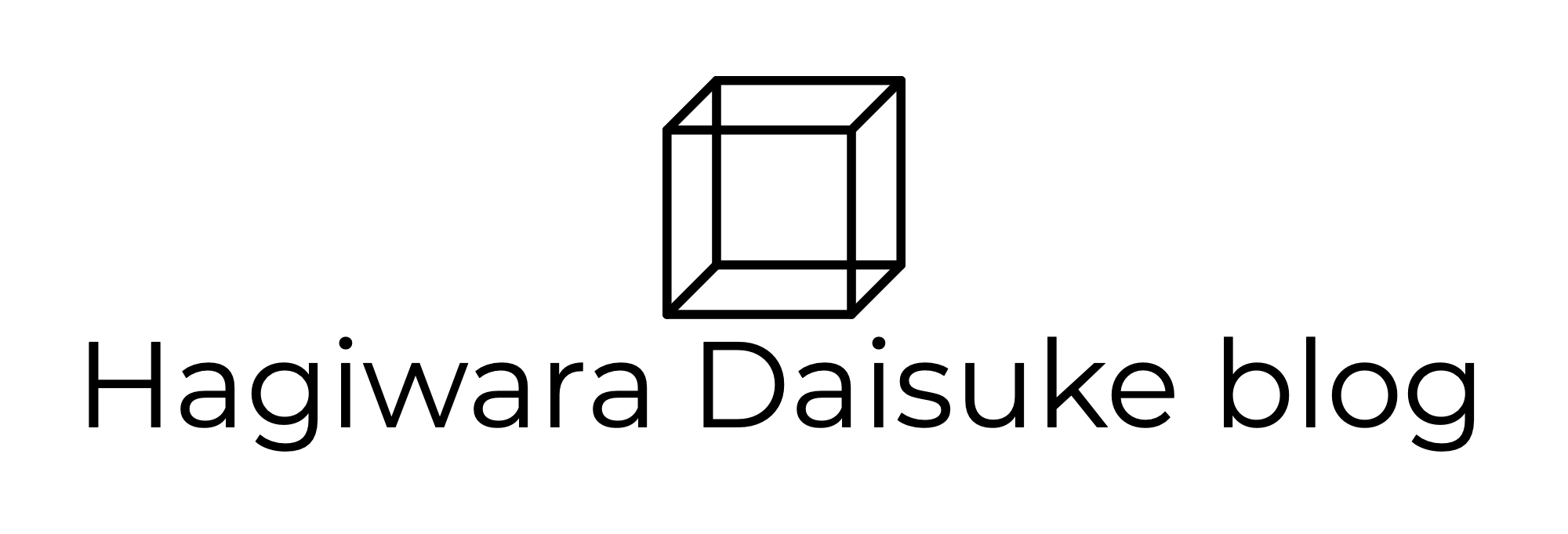昼下がり、僕は一人レストランにいた。
窓側の席に座り外を眺める。
懐かしい風景。
この席で僕ら三人は、色々な話をして泣いたり笑ったり、時にはケンカもした。
もう卒業して5年経つなんて信じられない。
肘をついて僕は一人窓の外を眺めていた。
2005年夏
「…ねぇ、ちょっと、ねぇ!」
誰かが僕に声をかけている。
「ん…?あぁ、ごめんごめん。」
僕は車の後部座席に座っている。
知らぬ間に寝てしまってたらしい。
「佐藤は本当よく寝るな~。」
三田邦宏は運転席から笑いながら話す。
「ちょっと三田君、笑い事じゃないよ。まったくペーパードライバー佐藤様は呑気でいいわね。」
助手席に座っているのは同じ学校に通う西村早紀だ。
「うるさいなぁ西村、三田ごめんごめん。」
僕はちょっと気まずくなって話す。
「ちょっと私にも謝罪の言葉はないの?私も頑張って起きてるんだから。」
西村はむくれて言う。
寝ぼけ眼で僕は返す。
「はいはい。すんませんです。」
僕ら三人は同じ学校に通っていて、みんな来年卒業する。
「卒業したら三人で休み合わせるの難しくなるかもしれないし、
行けるうちにちょっと遠出しないか?俺の車があるし。」
そう言い出したの三田だった。
三田とは、入学してすぐに仲良くなった。
きっかけは忘れたが、明らかに他の同級生とは違う空気を持っていて、
何となく気になる存在だったことを覚えている。容姿端麗で、まぁ早い話モテる男だった。
見た目が華やかな人間にありがちな鼻につく感じは全くなく、気取らない良い奴だ。
西村早紀とは、最初から会う機会が多く自然に話すようになった。
見た目はそこそこ可愛いが、気が強く我が道を行くような女の子。
サバサバした性格が僕は気に入っていた。
僕が三田とよく行っていたレストランで彼女はアルバイトをしていて、
それをきっかけに少しずつ仲良くなっていった。
「いいよいいよ。むしろ寝てくれるってのは、俺の運転を信用してくれてるってことだろ?」
三田はバックミラーで僕の顔を見て言う。
「そう、その通り!」
僕がわざと偉そうに言うと、
西村がため息まじりに呆れて続ける。
「調子いいわね。まったく。」
都心から車で3時間。
僕らは目の前に広がる景色に見とれていた。
「やっぱりこの辺はそんなに混んでないね。穴場だよ穴場。」そろそろ着くらしく、
三田は嬉しそうに話した。
広々とした海浜公園の広場。週末にも関わらず、それほど混雑もしていない。
僕ら三人は車から降り、積み込んだバーベキュー道具を用意し早々と準備を進める。
三人とも酒好きだが、今回ドライバーである三田が飲めないので”酒はなし”
というルールは決めていた。
そんなわけで持ってきたクーラーボックスの飲み物は、烏龍茶やジュースしかない。
そのことに三田が気付き言った。
「あ、なんだ、本当に酒は買わなかったの?二人で飲んでてよかったのに。」
「本当?悪いなぁ。じゃ駅前にコンビニがあったから買ってきまぁす。」
行こうとする僕に西村がムッとした顔で言う。
「ちょっと!ダメ!一緒に買い出し行った時、
{今回は健全に酒抜きでいこう。}そう言ったのは佐藤君でしょう?」
「そうだっけ?いいんじゃない?三田はいいって言うんだから。」
「ダメです。」
「どうしても?」
「ダメ!」
西村は言い出したら、絶対自分の意見を曲げないのだ。
出会った頃から変わらない。
しばらくの間、からかいながら僕と西村の口論は続く。
「西村は、もうちょっと柔軟性があった方がいいよ。だから彼氏ができねぇんだ。」
「ちょっと!何よそれ。私はできないんじゃなくて、作ってないだけよ。
好きな人くらいはいるんだから。」
「んじゃなおさら、柔軟性が大切。」
「本当うるさいわね。佐藤君は結局お酒飲みたいだけでしょうが。」
「まあね。」
「…二人とも気を遣わせて悪いね。今日車を家に置いてから飲みに行こうか?」
「うむ。賛成。」
「そうね、それもいいかもね。」
僕と西村は笑顔で頷いた。
それから僕ら三人は持ち込んだ肉や魚、野菜を全部あっという間に食べてしまった。
食べ終わってのんびりしてると三田が立ち上がり車の方に向かった。
バドミントンのラケットと羽を持ってこっちに戻ってくる。
「食後に運動しない?」
ラケットを上げて話す。
三田は運動神経が良いのだ。
しかしながら僕は全くもって運動オンチだ。
それにあんまり運動する気になれない。
「あ、俺はいいや。苦手だから二人で遊んでていいよ。」
「いいじゃない、やりましょうよ。」
と西村。
「いいよいいよ。二人でやってきて。」
二人は僕を誘うことをあきらめ、広い所でバドミントンを始めた。
広場に座って三田と西村の姿をぼーっと眺める。
潮風が心地好い。
”ずっとこんな風に三人で遊べたらいいな”
僕は心からそう感じていた。
しばらく遊んだ後、三田と西村は戻ってくる。
三田が笑顔で話す。
「そろそろ帰ろうか?」
僕は西村をそっと見ると彼女は笑顔で頷き話す。
「佐藤君、あれを出したまえ。」
「はい、おおせのままに。」
僕らのワザとらしいやり取りを不思議そうに見てる三田に僕は小さな包みを渡した。
「ん?俺に?開けていいか?」
僕と西村は笑顔で頷く。
意味が分からない、といった表情の三田は包みを破く。
「ブレスレット?」
「ほら、俺と西村が買い出しに言ったじゃない?そん時に予算が少し余ってね。
安物だけど同じの三つ買ったんだよ。」
僕と西村は右腕を見せる。
「三人お揃いかぁ。いいねぇ。」
三田は嬉しそうにブレスレットをつける。
帰りの車の中、明らかに眠そうな僕と西村を見て三田は言う。
「佐藤も西村も寝てていいよ。」
「いやいや、それは流石に悪いよ。」
「そうよ。でも楽しかったね。また行きましょう!」
西村は楽しそうに話した。
それから数時間後、結局ドライバーの三田以外は眠ってしまった。
この時の僕らには
その後起こることなんて想像もできなかった。
どのくらい時間が経ったのか…
車の急ブレーキと、強い衝撃で目が覚める。
「痛ってぇ…二人とも大丈夫か?ごめん…人が急に飛び出してきて。」
「あ、あぁ俺は大丈夫だけど…西村?おい!」
西村はうっかりシートベルトを外してしまっていて、車の窓に頭を強打してしまっていたようだ。
「ダメだ。意識が戻らない。救急車呼んでくれ!早く!」
「あぁ…」
三田は青冷めた顔で、慌てて119番に電話をかけた。
西村は検査の結果幸い軽い脳震盪と診断され、数時間後には意識も戻った。
僕は急いで彼女の実家のご両親に連絡も済ませた。
しかし
なぜか彼女の中で僕ら二人の記憶だけが、ポッカリと抜け落ちてしまっていた。
僕が病室にいたのだが、意識が戻った西村はうつろな目で僕を見て言った。
「誰…ですか?」
「西村…誰だか分からないのか…?佐藤だよ。今三田も呼んでくるから。」
「…すみません。思い出せません。私、気を失ってたんですか?
ここは病院?全然覚えてないんです…。」
「おい…本気か?」
しばらくして三田も病室へやってきた。
「西村…さん。俺達のこと分からないの?」
三田はゆっくりと話しかける。
「…はい。すみません。申し訳ないのですが、一人にして頂けませんか。」
西村は怯えた様子で言った。
「そんな…」
僕は、唖然としたまま動けなくなった三田の手を引っ張り、
ひとまず病室を後にしようとすると病室のドアが激しく開いた。
「早紀!」
彼女の両親だった。
「もう娘には構わないで下さい!」
それが彼女の両親からの言葉だ。
僕らは頭を下げ、病室を後にする。
帰り際僕らは黙ったままだったが、三田が口火をきった。
「すまない…」
「謝るなって、意識戻ってよかったじゃないか。
三田が来るまでいくつか質問したんだけど…
俺達のこととバーベキューのこと以外はしっかり覚えてるんだ。
悲しいけれど、三田は悪くないよ。運転任せて寝てしまった俺のせいでもある…
ご両親がああ言うのも仕方ないよね…」
三田は青ざめた顔のまま話す。
「いや、仕方なくないよ。俺の責任だ。」
それっきり、僕らは話さずに別れた。
しばらくして西村は無事退院できたらしく、何度か学校で見かけることがあった。
しかしながら向こうから話しかけては来なかったし、僕の方からも声はかけられずにいた。
なんとなく彼女を見ると友達と楽しそうに笑っている。
元気ならそれでいい。そう考えるようにして
そっと彼女を見守っていた。三田はしばらく学校を休んでいたが、
最近復帰し常に浮かない顔をしている。
極端に口数が減ってしまい、以前の明るくて優しい三田はどこにもいなかった。
三田には何度か話しかけたが、明らかに僕を避けていたこともあり、
次第に僕らは離れてしまった。そのまま秋になり冬が来て、やがて桜が咲き始める頃。
僕らは卒業式を迎える。
式を終え、帰り支度をしている僕に三田は話しかけてきた。
「…佐藤久しぶり。」
いきなり話しかけられ僕は驚いた。
「あぁ…久しぶり。」
「一緒に帰らないか?」
明らかに緊張しながら三田は話した。
僕はそんな姿が可笑しくて笑った。
三田も恥ずかしそうに以前のような笑顔を見せた。
学校を出ると三田は話しかけてきた。
「なぁ、よく三人で行ったあの店寄って行かない?」
「あぁいいね。行こうか。」
僕ら三人が疎遠になってしまって以来、すっかり行かなくなった店だ。
”もう西村はアルバイトしていないはずだよな”
僕はそう思いながら店に入り、三田の後に続いて歩いていく。
三田の進む奥の席には見覚えのある女の子が座っていた…
「佐藤君、久しぶり。」
西村はあの時のまま笑顔で僕らを迎える。
「え?記憶戻ったのか?」
僕は訳が分からず尋ねた。「あ、佐藤…言いづらいんだけど…」
三田は気まずそうに話した。
「俺達、付き合ってるんだ。」「は?いやいや、そういう問題じゃなくてさ、あの…何ていうか…」見兼ねたように、西村が話す。
「佐藤君、本当にごめんなさい。
私本当は、あの事故の三日後くらいには記憶戻ってたのよ。」「え?」三田が話を続ける。
「西村のことに責任を感じてね。ご両親にはもちろん責められたけど、毎日見舞いに行ってたんだ。何とか西村を看病したくて。何日か通ったらようやく認めてくれてね。
車に落ちてたこれがきっかけで少しずつ西村の記憶が戻ったんだ。」
袖をまくって、あの時のブレスレットを見せた。僕も袖をまくって見せる。
「佐藤もまだ付けてくれてたんだな。」
三田は本当に嬉しそうに話した。
「きっとこのブレスレットのおかげで思い出すことができたんだと思う。」
西村もブレスレットを見せる。
僕は困惑しながら話す。
「う~ん、でもなんで俺を無視したんだよ。」
西村はうつむいて話した。
「無視なんてしたつもりはなくて…なかなか話しかけられなかったの。」
「なるほど。つまりお前ら二人は俺を騙したのか…」
僕はため息混じりにつぶやいた。
「すまん…なかなか言い出すタイミングがなくて…」
三田も申し訳なさそうに話す。
「まったく…しかもお前ら付き合ってるって何だよ。」
僕は半分安心し、半分呆れながら続けた。
「ま、いいや。とりあえず納得しましたよ。無理矢理だけど。」
「すまん…」
「ごめんなさい…」
二人が頭を下げる。
「ただし、お前ら何かおごれよ。」
僕は二人を見つめて笑った。二人も僕を見て笑う。
店でしばらく三人で話した。
こんなに安心しながら話すのは久しぶりだった。
三人で歩く帰り道。
今日で最後だ。
僕は立ち止まり二人に話しかける。
「ちょっと見て、すげえ綺麗じゃない?」
三人で立ち止まり空を見上げる。
「あぁ…本当綺麗だな。
いつも通る道なのに、ちゃんと見たの初めてかも。」
三田は話した。
街はちょうど夕暮れで
遠くの空に浮かぶコントラストは本当に美しかった。
「見慣れた風景も捨てたもんじゃないね。」
西村も空を見上げてつぶやいた。
僕らの影は長くのびる。
時間は過ぎる。
今はまだ頼りないけれど、僕らはきっと強く生きていけるだろう。
何より、
”僕”は、また”僕ら”を取り戻せたのだ。
それがたまらなく嬉しかった。
僕はこれから東京の大学へ進学する。
三田と西村は地元の大学へ行くことになったらしい。
僕らは別々の道を行く。
でもずっと繋がっている。
これからもずっと。

萩原大介(ハギワラダイスケ )切ないメロディーで心の音を鳴らす孤高の唄い人。 「風景の唄」「希望の唄」「夕凪の唄」アルバム3枚全国リリース。 FMaiai毎週金曜日12時〜番組パーソナリティ。 歌を歌いながら文章を書いています。 blog毎日更新。 短編小説は不定期に新作をアップ。